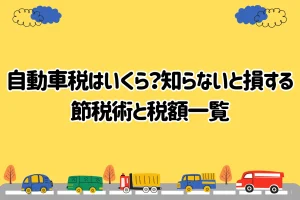ブレーキパッドは安全に直結する部品。
音・効き・警告灯に異常があれば、放置せずプロに交換を依頼するのが最善です。
- おすすめする人:走行距離3万km以上、異音・警告灯・効きの違和感を感じる人
- メリット:安全性の向上、制動力の安定、ローター損傷防止
- デメリット/注意点:放置すると高額修理や事故のリスク
「最近、ブレーキを踏むとキーキー音がする…」「このまま乗り続けても大丈夫なんだろうか?」「ディーラーは高そうだし、かといって安い業者で安全性がおろそかになるのは怖い」。
家族を乗せる大切な愛車だからこそ、ブレーキパッドの交換に関する悩みは尽きませんよね。
この記事では、そんなあなたの不安や疑問をすべて解決します。国家資格を持つプロの整備士が、ブレーキパッド交換の適切な時期を見極めるサインから、ディーラーやカー用品店ごとの詳細な費用比較、そして本当に信頼できる業者の選び方まで、専門的な知識を誰にでもわかるように徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたはもう業者に言われるがままではありません。ご自身の車の状態を正しく理解し、安全性と費用の両面で納得のいく最適な選択ができるようになっているはずです。
【忙しいあなたに】1分で読める簡単要約
ブレーキパッドは命を守る最重要部品。
「キーキー音」「ブレーキの効きが悪い」「警告灯点灯」は、交換時期のサインです。
費用は軽自動車で1万円前後、高級車で3万円以上。
安さだけで選ぶと品質リスクが高く、結果的に高額修理になることも。
交換は認証整備工場またはディーラーで早めに実施が安全。
DIY交換は特定整備に該当し、事故や法律違反の危険があります。
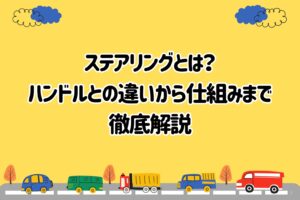
ブレーキパッド交換の時期を見極める5つの危険なサイン

ブレーキパッドの交換時期は、単に走行距離だけで決まるものではありません。車が発する「SOS」に気づくことが、安全と余計な出費を防ぐ鍵となります。ここでは、プロが必ずチェックする5つの危険なサインを解説します。
ブレーキパッド交換時期は「音」「感触」「警告灯」で判断可能です。
キーキー音はインジケーターが鳴らす警告で、まだ走行は可能ですが早めの交換が必要。
ゴリゴリ音や効きの低下は危険信号で、ブレーキローター損傷や制動不能の恐れがあります。
特に厚み3mm以下は即交換推奨。
車検時だけでなく、定期点検でプロに残量確認してもらうのが最も確実です。
【サイン1】ブレーキから「キーキー」と甲高い音がする
ブレーキを踏んだ際に「キーキー」「シャリシャリ」といった甲高い金属音が聞こえたら、それは交換時期が近づいている最初のサインです。多くの国産車にはパッドウェアインジケーターという金属製の部品が取り付けられています。パッドがすり減って一定の厚さになると、このインジケーターがブレーキローターに接触し、意図的に警告音を発生させる仕組みです。
この段階であればまだ走行は可能ですが、決して放置してはいけません。音を無視し続けると、インジケーターがローターを傷つけ、結果的にブレーキローターまで交換が必要となり、修理費用が数万円単位で高騰する可能性があります。
【サイン2】「ゴーゴー」「ゴリゴリ」という低い異音がする
もし音が「キーキー」から「ゴーゴー」「ゴリゴリ」といった鈍く低い音に変わったら、それは極めて危険な状態です。この音は、パッドの摩擦材が完全になくなり、土台である金属製のバックプレートが直接ブレーキローターを削っている音です。
この状態ではブレーキが正常に機能せず、制動距離が著しく伸びるため、重大な事故に直結する可能性が非常に高いです。ただちに運転を中止し、安全な場所に停車してレッカーサービスなどを手配してください。絶対にそのまま乗り続けてはいけません。
【サイン3】ブレーキの効きが悪くなった・ペダルが深くなった
「以前よりブレーキペダルを深く踏み込まないと車が止まらない」「ペダルの感触がフワフワする」といった感覚も、パッドの摩耗を示す重要なサインです。パッドが薄くなると、その分ピストンが多く押し出され、より多くのブレーキフルードが必要になるため、ペダルの踏みしろが深くなります。
制動力の低下は、追突事故のリスクを直接的に高めます。特に高速道路や下り坂での運転では、このわずかな変化が命取りになりかねません。少しでも効きに違和感を覚えたら、すぐに専門家による点検を受けましょう。
【サイン4】ブレーキ警告灯が点灯した
メーターパネルに表示される(!)マークのブレーキ警告灯は、パーキングブレーキの作動を知らせるだけではありません。走行中にこの警告灯が点灯した場合、ブレーキフルードの量が基準値を下回っている可能性が高いです。
ブレーキパッドが摩耗すると、その隙間を埋めるためにブレーキフルードがキャリパー側へ移動し、リザーバータンク内の液面が低下します。つまり、警告灯の点灯はパッドの摩耗がかなり進んでいることを間接的に示しているのです。警告灯が点灯したら、速やかに整備工場で点検を受けてください。
【サイン5】パッドの厚みが3mm以下になった
最も確実な判断基準は、ブレーキパッドの残量(厚み)です。新品のパッドは約10mmの厚みがありますが、これが3mm以下になったら交換時期です。2mmを下回ると、制動力の低下やブレーキローターへのダメージリスクが急激に高まるため、即時交換が必要な危険水域と言えます。
走行距離の目安としては、運転スタイルにもよりますが、一般的に前輪が3万〜5万km、後輪が5万〜10万kmとされています。ただし、ハイブリッド車やEVは回生ブレーキがあるため、10万km以上持つことも珍しくありません。定期点検やタイヤ交換の際に、プロに厚みをチェックしてもらうのが最も確実です。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺異音を感じたら早めに整備工場で確認を。
走行中の「ゴー音」や「金属の擦れる音」は事故直前のサインです。
厚みを自分で見るなら、ホイールの隙間からライトで確認できます。
目視できない場合は、タイヤ交換時や法定点検時に必ず整備士へ依頼しましょう。
- ブレーキ音は初期警告サイン。放置でローター交換が必要に。
- 「ゴリゴリ音」は末期症状で即走行中止が原則。
- ペダルの踏み込み感・警告灯・残厚3mm以下は交換ライン。
【車種・依頼先別】ブレーキパッド交換の費用相場を徹底比較
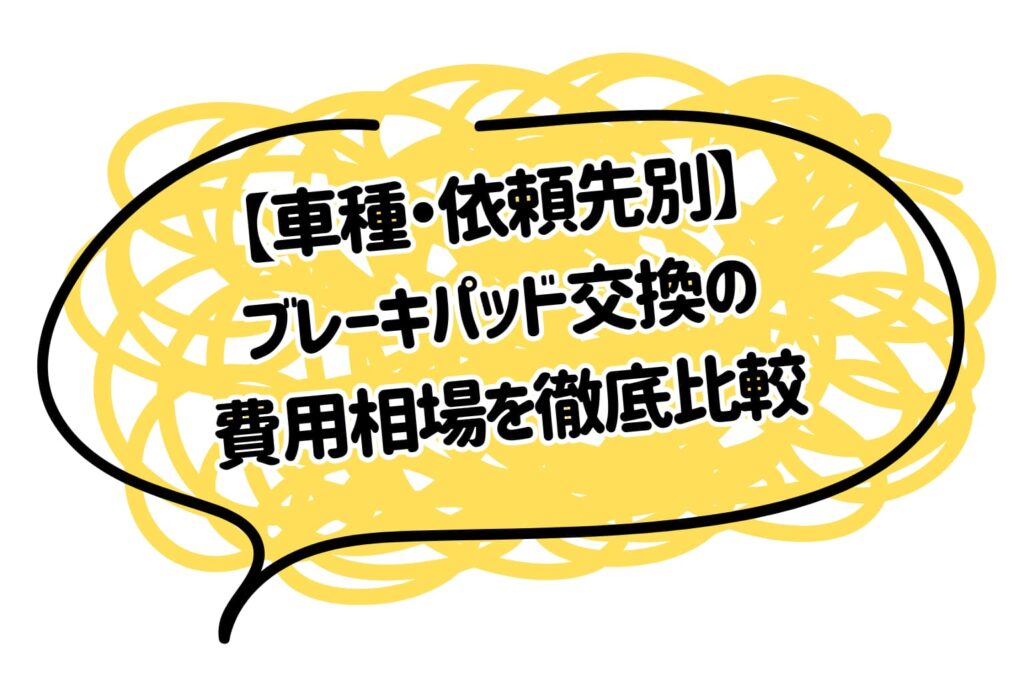
ブレーキパッド交換で最も気になるのが費用です。ここでは、費用の内訳から車種別・依頼先別の具体的な相場まで、あなたが損をしないための情報を詳しく解説します。
ブレーキパッド交換費用は、部品代+工賃で構成されます。
軽自動車で1〜1.5万円、普通車で2万円前後、輸入車は5万円以上になることも。
ディーラーは純正品・保証付きで信頼性が高く、整備工場やカー用品店は安価。
社外品を選ぶ場合は、JIS認証・Eマーク取得品など、安全規格を満たした製品を選びましょう。
ブレーキパッド交換費用の内訳
ブレーキパッド交換の費用は、大きく分けて「部品代」と「工賃」の2つで構成されます。
- 部品代: ブレーキパッド本体の価格。メーカー純正品か、性能や価格帯が多様な社外品かで大きく変動します。
- 工賃: 交換作業にかかる技術料。依頼する業者や、前輪(フロント)か後輪(リア)かによって変わります。
一般的に、部品代と工賃を合わせた総額で費用を考えることが重要です。
【車種別】ブレーキパッド交換の費用相場
車のサイズや重量によって、使用するブレーキパッドの価格や工賃は異なります。以下に、一般的な車種カテゴリー別の費用相場(前輪または後輪のどちらか一方)をまとめました。
| 車種カテゴリー | 費用相場(部品代+工賃) | 具体的な車種例 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 10,000円 ~ 15,000円 | N-BOX、タント、スペーシア |
| コンパクトカー | 12,000円 ~ 20,000円 | ヤリス、フィット、ノート |
| ミニバン・SUV | 15,000円 ~ 25,000円 | ヴォクシー、セレナ、ハリアー |
| セダン・高級車 | 18,000円 ~ 30,000円 | プリウス、クラウン、カローラ |
| 輸入車 | 25,000円 ~ 50,000円以上 | BMW、メルセデス・ベンツ |
※上記はあくまで目安です。前後両方を交換する場合は、約2倍の費用がかかります。
【依頼先別】ディーラー・カー用品店・整備工場の料金と特徴
交換を依頼できる業者には、それぞれ特徴があります。あなたの価値観に合った場所を選ぶための比較表をご覧ください。
| 依頼先 | 費用相場 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ディーラー | 高い | ・メーカー純正品で安心 ・車種に精通した整備士が作業 ・整備保証が手厚い | ・工賃、部品代ともに高額 ・社外品を選べないことが多い |
| カー用品店 | 普通 | ・社外品など部品の選択肢が豊富 ・キャンペーン等で安くなることがある ・店舗数が多くアクセスしやすい | ・整備士の技術力にばらつきがある ・複雑な作業には対応できない場合がある |
| 街の整備工場 | 安い~普通 | ・工賃が比較的安い ・柔軟な対応(持ち込み等)が可能な場合も ・地域密着で相談しやすい | ・工場の技術力や設備に差がある ・信頼できる工場を探す手間がかかる |
費用を安く抑える3つのコツ
安全性を確保しつつ、賢く費用を抑える方法も存在します。
- 複数の業者から相見積もりを取る: 同じ作業内容でも業者によって価格は異なります。最低2〜3社から見積もりを取り、内容と価格を比較検討しましょう。
- 車検や法定点検と同時に依頼する: 車検などではタイヤを外す工程が含まれるため、ブレーキパッド交換の工賃が割引されたり、単独で依頼するより安くなったりする場合があります。
- 信頼できる社外品を検討する: 純正品にこだわらなければ、性能が同等で価格が安い優良な社外品も多く存在します。業者に相談し、車の使い方に合った製品を提案してもらいましょう。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺安さだけで選ぶとブレーキ性能や寿命に影響します。
相見積もりを取ることで1〜2割安くできるケースも。
また、車検や点検と同時依頼すれば工賃割引を受けられることも多いです。
信頼できる業者を見つけ、安全とコストのバランスを重視しましょう。
- 費用は軽自動車1〜1.5万円、普通車1.5〜3万円が目安。
- ディーラーは安心・保証重視、整備工場は価格重視。
- 社外品の選択肢でコスパ改善可能だが品質要確認。
【プロに聞く】ブレーキパッド交換はどこに頼むのが正解?信頼できる業者の選び方

「結局、どこに頼むのが一番良いの?」という疑問にお答えします。安さだけで選ぶのは危険です。ここでは、あなたの価値観に合った依頼先の選び方と、悪質な業者に騙されないためのチェックポイントを伝授します。
ブレーキパッド交換は、安全に直結するため、国の認証を受けた整備工場で行うのが基本です。
認証工場(青い看板)は、分解整備を行う資格を持ち、整備保証も付きます。
見積書の内容が明確で、整備士が丁寧に説明してくれる業者は信頼できます。
価格だけでなく、施工後の保証や評判もチェックしましょう。
あなたの価値観に合った依頼先の選び方
最適な依頼先は、あなたが何を最も重視するかによって決まります。
- 「とにかく安心感が第一!」品質重視派のあなたへ: ディーラーが最適です。費用は高くなりますが、メーカー純正部品と専門知識を持つ整備士による作業は、何物にも代えがたい安心感を与えてくれます。
- 「価格と選択肢の多さが魅力!」コスパ派のあなたへ: カー用品店が良いでしょう。様々な社外品から予算や好みに合わせてパッドを選べ、比較的リーズナブルに交換が可能です。
- 「安さと信頼性を両立したい!」堅実派のあなたへ: 信頼できる街の整備工場がおすすめです。ディーラーより安く、カー用品店より専門的な相談ができる場合も。良い工場を見つけられれば、最高のパートナーになります。
信頼できる業者を見分ける3つのチェックポイント
良い業者を見分けるには、いくつかのポイントがあります。
- 見積もりが明確で説明が丁寧か: 部品代と工賃の内訳がきちんと記載されており、なぜこの作業が必要なのか、どんな部品を使うのかを素人にも分かりやすく説明してくれる業者は信頼できます。
- 「認証工場」の資格を持っているか: 国土交通省が認可した「認証工場」は、ブレーキのような重要保安部品を分解整備するために必要な設備と技術基準を満たしています。工場の入り口や事務所に青い認証看板が掲げられているか確認しましょう。
- 口コミや評判が良いか: 実際にその業者を利用した人のレビューは貴重な情報源です。Googleマップの口コミや地域の評判などを参考に、誠実な対応をしているかを確認しましょう。
整備士が語る「安いブレーキパッド」の落とし穴
「ネットで激安のブレーキパッドを見つけたから、これを使ってもらいたい」と考える方もいるかもしれません。しかし、プロの視点から見ると、極端に安い製品には注意が必要です。安価なパッドは、ブレーキの効きが甘い、すぐにキーキー音が鳴き出す、ブレーキダストでホイールが真っ黒になる、寿命が極端に短いといったデメリットを抱えていることが少なくありません。
安全に関わる最重要部品だからこそ、安さだけを追求するのは危険です。信頼できるメーカーの製品を選ぶことが、結果的に安全とコストパフォーマンスの両方を満たすことに繋がります。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺店舗選びでは「整備保証の有無」を最初に確認。
また、パッド交換後に異音や片効きが出た場合は、すぐ再点検を依頼してください。
格安チェーンよりも地域密着型工場のほうがアフター対応が早く、信頼関係を築きやすい傾向があります。
- 「国認証工場」マークがある店舗は信頼性が高い。
- 見積書に部品・工賃が明記されているかが品質の指標。
- ネット口コミよりも実店舗の対応・説明力が重要。
ブレーキパッド交換のDIYは危険?プロが推奨しない3つの理由

費用を抑えるために「自分で交換できないか?」と考える方もいるでしょう。結論から言うと、ブレーキパッドのDIY交換はプロとして絶対に推奨しません。その理由は以下の3つです。
ブレーキパッド交換は、国家資格を持つ整備士のみが安全に行える作業です。
道路運送車両法により、無資格での他人の車整備は違法。
また、トルクレンチやピストンツールなどの特殊工具が必要で、
締付不足や取付ミスは走行中の制動不能につながります。
命を預ける部分だからこそ、DIYではなくプロに任せることが鉄則です。
理由1:重大な事故に直結するリスク
ブレーキは、あなたの命だけでなく、同乗者や周囲の人の命も預かる最重要保安部品です。もし取り付けに不備があれば、走行中にブレーキが効かなくなったり、タイヤがロックしたりする可能性があります。ほんの少しの作業ミスが、取り返しのつかない大事故を引き起こすリスクがあるのです。
理由2:専門知識と特殊工具が必要
ブレーキパッドの交換には、キャリパーピストンを戻すための専用工具(ディスクブレーキピストンツール)や、ボルトを規定の力で締め付けるためのトルクレンチが必須です。これらの工具がないまま作業を行うと、部品を破損させたり、適切な取り付けができなかったりします。また、車種ごとに異なる構造や締め付けトルク値を正確に理解している必要があります。
理由3:法律上の「特定整備」に該当する
ブレーキシステムの分解整備は、道路運送車両法で定められた「特定整備(分解整備)」に該当します。他人の車を整備するためには、国から認証を受けた工場でなければならず、無資格での作業は法律で禁じられています。自分の車を整備すること自体は違法ではありませんが、それだけ専門性と責任が問われる作業であることの証明です。失うものに対して、得られるメリット(工賃の節約)はあまりにも小さいと言えるでしょう。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺「自分でやれば安い」と考えがちですが、整備不良による事故は保険も適用外。
万一トラブルが発生した場合、自己責任では済まされません。
資格を持つ整備士に依頼し、施工記録を残すことが安全と法的保護につながります。
- ブレーキは国が定める「特定整備(分解整備)」に該当。
- 工具・締付トルク・車種構造の知識が必須。
- 不備があれば重大事故や法律違反になる。
ブレーキパッド交換に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、お客様からよくいただく質問についてお答えします。
- ブレーキパッドとブレーキローターは同時に交換すべき?
-
同時交換が理想ですが、必須ではありません。
ブレーキローターもパッドと同様に摩耗する消耗品です。新品のパッド性能を100%引き出すためには、同時にローターも新品にすることが最も理想的です。ただし、ローターの摩耗が少なければ、パッドのみの交換でも問題ありません。一般的には「パッド交換2回につき、ローターを1回交換する」のが目安とされています。点検時にローターの状態を確認してもらい、判断を仰ぎましょう。 - ブレーキフルードも交換した方がいい?
-
同時に交換することを強くおすすめします。
ブレーキフルードは時間と共に劣化し、水分を含むとブレーキ性能を低下させる原因になります。一般的に2年ごとの交換が推奨されており、車検のタイミングで交換する方が多いです。パッド交換の際に同時に作業すれば、工賃を節約できるメリットもあります。安全のためにも、合わせて交換を検討しましょう。 - 持ち込みでの交換は可能?
-
業者によりますが、注意が必要です。
自分で購入したブレーキパッドの持ち込み交換に対応してくれる整備工場もあります。しかし、ディーラーやカー用品店では断られるケースが多いです。また、持ち込みOKの場合でも、工賃が割増になったり、取り付けた部品や作業に関する保証が一切受けられなかったりするデメリットがあります。持ち込みを検討する際は、事前に業者へ確認し、リスクを理解した上で依頼しましょう。
まとめ

ブレーキパッドの交換は、愛車の安全を維持するために欠かせない重要なメンテナンスです。ブレーキからの異音や警告灯は、車からの危険なサインです。決して放置せず、早めに専門家に相談してください。
交換費用は車種や依頼先によって様々ですが、ディーラー、カー用品店、整備工場の特徴を理解し、相見積もりを取ることで、ご自身の予算と価値観に合った最適な選択が可能です。DIYでの交換は重大なリスクを伴うため、必ず国が認めた信頼できるプロに任せましょう。
この記事で得た知識を元に、自信を持って業者と話し、納得のいくブレーキパッド交換を行ってください。それが、あなたとあなたの大切な家族の安全を守るための、最も賢明な選択です。
![HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](https://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/cc3d9ca1-c88b-463e-af8f-67dd29cc5449.png)