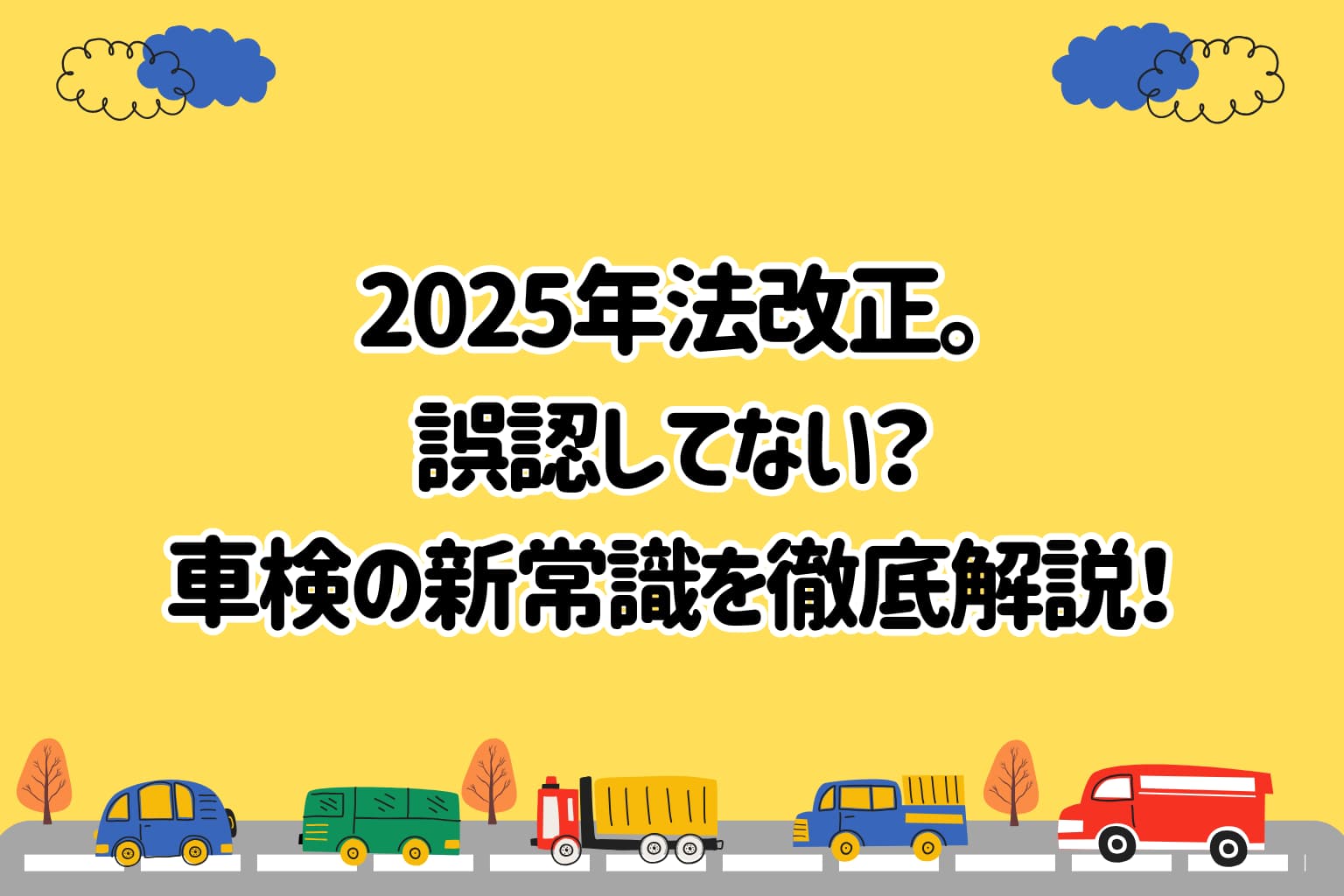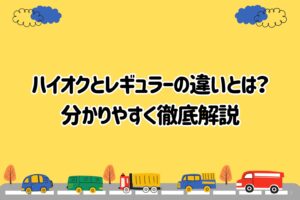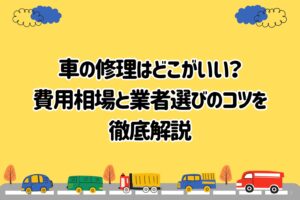「そろそろ愛車の車検だけど、正確にはいつから受けられるんだっけ?」「新車から5年目、費用は前回と変わるのかな?」そんな疑問をお持ちではありませんか?
車検は数年に一度のことなので、つい満了日を忘れてしまったり、制度の変更に気づかなかったりすることもありますよね。特に、毎日お仕事やご家族のために運転される方にとって、車検切れは絶対に避けたい事態です。
ご安心ください。この記事を読めば、あなたの車の正しい車検期間から、2025年の法改正による変更点、年数による費用の違い、そして万が一車検が切れてしまった場合の対処法まで、車検に関するあらゆる疑問が解決します。
先に結論をお伝えすると、一般的な自家用車(普通車・軽自動車)の車検は、新車登録から3年後、それ以降は2年ごとです。これは10年を超えても変わりません。
この記事で、複雑に思える車検のルールをスッキリ整理し、賢くお得に車検を乗り切りましょう。
- 2025年4月から車検は満了日の「2ヶ月前」から受けられるようになる。
- 自家用車の車検期間は10年超えても原則「2年ごと」で変わらない。
- 13年・18年経過で重量税や自動車税が上がる(いわゆる“増税”)
- 車検切れでの運転は免許停止など重い罰則あり。
- 「仮ナンバー」や「積載車」で車検切れの車を合法的に運ぶ手段がある。
2025年4月から車検制度が一部変わり、「10年超の車も2年車検のまま」でOKになるなど、以前より柔軟なルールになりました。ただし、古い車には重量税や整備費が高くなるなどの負担も増える可能性があるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。また、車検切れで公道を走ると重大な違反になるため、満了日を忘れずに管理することも重要なポイント。車検の仕組み・費用・注意点を知っておけば、急なトラブルや無駄な出費を避け、安心して愛車に乗り続けられます。

【結論から】見るだけでわかる!車種別の車検有効期間一覧
![見るだけでわかる車種別の車検有効期間一覧 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/見るだけでわかる車種別の車検有効期間一覧-1024x683.jpg)
車の種類や使い方によって、法律で定められた車検の有効期間は異なります。まずは、ご自身の車がどれに当てはまるか、一覧で確認してみましょう。
自家用乗用車(普通車・軽自動車)は初回3年、以降2年ごと
私たちにとって最も身近な自家用乗用車(3・5・7ナンバー)と軽自動車(自家用)は、新車登録後の初回検査が3年後、それ以降は2年ごとに車検を受ける必要があります。これは、日常的な利用を想定した場合、この期間で安全性を十分に維持できると考えられるためです。例えば、家族で乗るミニバンや通勤で使うコンパクトカー、セカンドカーとして人気の軽自動車などがこれに該当します。中古車で購入した場合でも、この「2年ごと」というサイクルは変わりません。
貨物自動車(トラックなど)は最短1年ごと
荷物を運ぶことを主目的とする貨物自動車は、乗用車よりも車検期間が短く設定されています。これは、走行距離が長く、車体への負荷も大きいため、より頻繁な点検が必要とされるからです。
軽貨物自動車(4ナンバーの軽自動車)は、初回・2回目以降ともに2年ごとです。しかし、車両総重量が8トン未満の普通・小型貨物自動車(1・4ナンバー)は、初回が2年、2回目以降は毎年車検を受けなければなりません。さらに、車両総重量8トン以上の大型トラックは、初回から1年ごとに車検が必要です。
バイクや特殊車両の車検期間は?
バイク(二輪自動車)も車検の対象です。排気量が250ccを超えるバイクは、新車登録から3年後、以降は2年ごとと、自家用乗用車と同じサイクルです。
また、「8ナンバー」で登録されるキャンピングカーなどの特殊用途自動車も、初回・2回目以降ともに2年ごとの車検が義務付けられています。ただし、同じ8ナンバーでも、人命救助に関わる消防車や救急車は、その重要性から毎年車検を受ける必要があります。
【一覧表】車種別・用途別の車検有効期間まとめ
| 車種 | ナンバー | 用途 | 初回車検 | 2回目以降の車検 |
|---|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 3, 5, 7 | 自家用 | 3年 | 2年 |
| 軽自動車 | 5, 7 | 自家用 | 3年 | 2年 |
| 軽貨物自動車 | 4 | 自家用 | 2年 | 2年 |
| 小型・中型貨物自動車 | 4, 1 | 自家用 | 2年 | 1年 |
| 大型貨物自動車(車両総重量8t以上) | 1 | 自家用 | 1年 | 1年 |
| バス・タクシー・ハイヤー | 2, 3, 5 | 事業用 | 1年 | 1年 |
| バイク(250cc超) | – | – | 3年 | 2年 |
| キャンピングカー | 8 | 自家用 | 2年 | 2年 |
| レンタカー(乗用車) | わ、れ | 事業用 | 2年 | 1年 |
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺まずは自分の車の「ナンバーの種類」をチェックして、適用される車検サイクルを確認しましょう!
- 自家用車(3・5・7ナンバー)は初回3年、以降2年が基本サイクル。
- 貨物車やバスなど事業用は1年ごとの車検が多く、使用頻度とリスクを考慮。
- バイクやキャンピングカーなどの特殊車両も独自のルールがある。
【いつから受けられる?】2025年4月から「2ヶ月前」に!車検のタイミング最新情報
![2025年4月から2ヶ月前に車検のタイミング最新情報 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/2025年4月から2ヶ月前に車検のタイミング最新情報-1024x683.jpg)
車検の有効期間がわかったら、次に気になるのは「いつから受けられるのか」ですよね。実は、このルールがまもなく変更されます。最新の法改正情報をしっかり押さえておきましょう。
原則は「満了日の1ヶ月前」から
現在のルールでは、車検は有効期間の満了日を迎える1ヶ月前から受けることができます。この期間内に車検を済ませれば、次回の満了日が前倒しされることなく、現在の満了日からきっかり2年後(または1年後)に設定されます。
もちろん、1ヶ月以上前に受けることも可能ですが、その場合は車検を受けた日から有効期間が計算されるため、次回の満了日が早まってしまい、少し損をしてしまいます。
【2025年4月1日〜】法改正で「2ヶ月前」から可能に!
2025年4月1日より、道路運送車両法が改正され、車検を受けられる期間が「満了日の2ヶ月前」からに拡大されます。これは、ユーザーにとって非常に大きなメリットがある変更です。
例えば、これまで5月15日が満了日だった場合、4月15日からしか受けられませんでしたが、改正後は3月15日から受けられるようになります。これにより、予約の選択肢が広がり、ご自身のスケジュールに合わせて、より柔軟に車検の計画を立てられるようになります。
なぜ変わる?法改正の背景とメリット
この法改正の背景には、自動車整備業界が抱える課題があります。日本では、3月に車の購入や登録が集中する傾向があり、その結果、車検も年度末に殺到していました。これにより、整備工場は繁忙を極め、ユーザーは予約が取りにくいという問題が発生していました。
期間が2ヶ月前に拡大されることで、車検の需要が分散され、整備工場の混雑緩和や整備士の労働環境改善につながることが期待されています。ユーザーにとっても、予約が取りやすくなる、余裕を持って見積もり比較ができるといったメリットがあります。
早く受けても損しない!満了日は変わらない仕組み
「2ヶ月前に受けると、その分だけ次回の車検が早まって損するのでは?」と心配されるかもしれません。しかし、ご安心ください。指定整備工場(民間車検場)で車検を受ければ、満了日の2ヶ月前に実施しても、次回の有効期間は現在の満了日から計算されます。
これは、指定整備工場が発行する「保安基準適合標章」という仮の車検ステッカーがあるためです。この標章の有効期間(15日間)内に運輸支局で手続きが完了すれば、満了日が短くなることはありません。ほとんどのディーラーや車検専門店はこの指定工場ですので、安心して早めに予約しましょう。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺まずは自分の車の「ナンバーの種類」をチェックして、適用される車検サイクルを確認しましょう!
- 従来の「1ヶ月前ルール」が「2ヶ月前OK」へ変更。
- 早めに予約できることで、年度末の混雑緩和や見積もり比較の余裕が生まれる。
- 満了日は変わらないので「早く受けて損」はない。
【費用は変わる?】10年・13年超えは要注意!車検期間と費用の関係
![10年13年超えは要注意車検期間と費用の関係 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/10年13年超えは要注意車検期間と費用の関係-1024x683.jpg)
「車は10年乗ると車検が1年ごとになって高くなる」と聞いたことはありませんか?これは現在では誤解ですが、年数が経過すると費用が変動するのは事実です。期間と費用の関係を正しく理解しましょう。
「10年超えると車検は1年ごと」は昔の話!現在は2年のまま
かつては、新車登録から10年を超えた自家用乗用車は、1年ごとに車検を受ける必要がありました。しかし、1995年の道路運送車両法改正により、この制度は廃止されています。
現在では、自家用乗用車や軽自動車であれば、初度登録から10年、13年、15年と経過しても、車検の有効期間は2年のままです。この点は、昔の知識のまま誤解されている方も多いので、しっかりと覚えておきましょう。車検期間自体は変わりませんが、費用面では注意が必要です。
ただし要注意!13年・18年で「税金」が上がる
車検の期間は変わりませんが、車の年数が経過すると税金の負担が増えます。特に注意したいのが、車検の際に支払う「自動車重量税」です。環境への負荷が少ない新しい車を優遇する観点から、新車登録から13年、さらに18年を経過したタイミングで税額が上がる仕組みになっています。
また、毎年支払う「自動車税(種別割)」または「軽自動車税(種別割)」も、ガソリン車は13年、ディーゼル車は11年を超えると重課(増税)の対象となります。
| 経過年数 | 自動車重量税(自家用・2年・1.5t以下の場合) |
|---|---|
| 〜12年 | 24,600円 |
| 13年経過 | 34,200円 |
| 18年経過 | 37,800円 |
なぜ?年数が経つと部品交換などで「整備費用」も高くなる傾向に
税金だけでなく、整備費用も車の年式に影響されます。走行距離が10万kmを超えたり、登録から10年が経過したりすると、ゴム製の部品やベルト類、サスペンションなど、さまざまな部品が経年劣化により交換時期を迎えます。
例えば、タイミングベルトやウォーターポンプ、ブレーキ関連部品などは、10万km前後が交換の目安とされています。これらの部品交換には数万円単位の費用がかかるため、結果として車検全体の費用が高くなる傾向にあります。
5年目・7年目の車検費用が高くなりやすい理由とは?
新車から3年目の初回車検に比べ、2回目(5年目)や3回目(7年目)の車検で「思ったより高かった」と感じる方は少なくありません。これには明確な理由があります。
まず、タイヤやバッテリー、ブレーキパッドといった消耗品の交換時期が重なることが多いのが5年目です。また、新車購入時に適用されていた「エコカー減税」が5年目以降は対象外となり、自動車重量税の割引がなくなることも一因です。さらに、メーカーの特別保証(エンジンやトランスミッションなど重要部品の保証)も5年で切れることが多く、万が一の故障修理が有償になる可能性も出てきます。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺車検そのものの期間は変わりませんが、維持費は年々高くなります。13年・18年での出費増に備えましょう!
- 車検期間は10年超えても2年のままだが、重量税などの税金がアップ。
- 13年・18年で環境負荷に応じた増税が適用。
- 経年劣化による部品交換が費用増の要因に。
【うっかり忘れても大丈夫?】車検切れのリスクとペナルティ、対処法を解説
![車検切れのリスクとペナルティ対処法を解説 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/車検切れのリスクとペナルティ対処法を解説-1024x683.jpg)
「気づいたら車検の有効期限が過ぎていた!」そんな時でも、慌てず正しく対処すれば大丈夫です。車検切れのリスクと、そうなってしまった場合の対処法を解説します。
車検切れで公道を走ると厳しい罰則が!
車検が切れた車を公道で運転することは、法律で固く禁じられています。もし車検切れの状態で運転(無車検運行)してしまうと、非常に重い罰則が科せられます。
- 違反点数:6点
- 行政処分:30日間の免許停止
- 刑事罰:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
たった一度の違反で「免停」となる重い処分です。事故を起こしていなくても、検問などで発覚すれば罰則の対象となります。絶対に車検切れのまま運転してはいけません。
自賠責保険も切れているとさらに重い罰則に
車検と同時に、強制保険である「自賠責保険」も期限が切れているケースがほとんどです。この状態で運転すると、無車検運行に加えて「無保険運行」となり、罰則がさらに加重されます。
- 違反点数:6点(合計12点)
- 行政処分:90日間の免許停止
- 刑事罰:1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
自賠責保険が切れていると、万が一事故を起こした場合、被害者への賠償はすべて自己負担となります。人生を左右するほどの大きなリスクを伴うため、車検の期限管理は非常に重要です。
| 違反内容 | 違反点数 | 行政処分 | 刑事罰 |
|---|---|---|---|
| 無車検運行 | 6点 | 30日間の免許停止 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 無保険運行 | 6点 | 30日間の免許停止 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 両方の違反 | 6点 | 90日間の免許停止 | 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金 |
※無車検と無保険は併合罪として扱われますが、違反点数は高い方が適用されるため6点となります。
車検切れに気づいたら?落ち着いて対処する3ステップ
もし車検が切れていることに気づいても、パニックになる必要はありません。以下のステップで冷静に対処しましょう。
- 絶対に運転しない: まずは公道を運転しないことを徹底します。たとえ自宅の駐車場から数メートルの移動でもNGです。
- 車検を依頼する業者を探す: ディーラーや整備工場、車検専門店などに連絡し、車検が切れている旨を伝えて見積もりと予約を取ります。
- 車を工場まで運ぶ手配をする: 車検を受けるには、車を整備工場まで運ぶ必要があります。公道は走れないため、特別な手続きが必要です。
車検切れの車を工場まで運ぶ方法:仮ナンバーと積載車
車検切れの車を整備工場まで移動させるには、主に2つの方法があります。
一つは、「仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)」を取得する方法です。市区町村の役所で申請し、自賠責保険証や車検証などを持参すれば、750円程度の手数料で発行してもらえます。ただし、有効期間は最長5日で、申請した運行経路しか走行できません。
もう一つの方法は、レッカー業者や車検業者に「積載車(キャリアカー)」で運んでもらう方法です。費用はかかりますが、手間がなく最も安全で確実な手段です。電話一本で手配できるため、時間がない方や手続きが面倒な方におすすめです。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺「ちょっとだけ運転」でもアウト!車検が切れたら絶対に公道を走らず、仮ナンバーか業者搬送を手配しましょう。
- 車検切れでの運転は6点減点+免停+罰金のリスク。
- 自賠責保険切れだとさらに重い罰則。
- 仮ナンバーで合法的に整備工場まで運べる。
【これで忘れない!】車検満了日の確認方法とスマートな管理術
![車検満了日の確認方法とスマートな管理術 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/車検満了日の確認方法とスマートな管理術-1024x683.jpg)
「うっかり車検切れ」を防ぐためには、満了日を正確に把握し、管理することが大切です。ここでは、誰でも簡単にできる確認方法と管理術をご紹介します。
一番確実!「自動車検査証(車検証)」で確認
最も正確な情報は、車のダッシュボードなどに保管されている自動車検査証(車検証)に記載されています。車検証の左下あたりにある「有効期間の満了する日」という欄を確認してください。そこに書かれている年月日が、あなたの車の車検満了日です。この日付までに次の車検を完了させる必要があります。
フロントガラスの「検査標章(車検シール)」の見方
フロントガラスの中央上部に貼られている四角いステッカーが検査標章(車検シール)です。このシールでも満了時期を確認できます。
- 外側(表面)から見える数字: 大きな数字が「月」、小さな数字が「年(和暦)」を示します。(例:大きな数字が「5」、小さな数字が「7」なら令和7年5月)
- 内側(裏面)から見える日付: より正確な満了年月日が記載されています。「〇年〇月〇日」と書かれているので、こちらを確認するのが確実です。
【2023年〜】電子車検証の場合はアプリで確認
2023年1月から、車検証がICカード化された「電子車検証」の交付が始まっています。この電子車検証の券面には、有効期間の満了日は記載されていません。
満了日を確認するには、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」をスマートフォンにインストールし、車検証のICタグを読み取る必要があります。アプリを使えば、有効期間の満了日はもちろん、所有者の氏名や住所など、詳細な情報をいつでも確認できます。
スマホアプリやカレンダーで賢くリマインド
車検満了日を確認したら、忘れないようにスケジュール管理ツールに登録しましょう。スマートフォンのカレンダーアプリやリマインダーアプリが非常に便利です。
満了日の2〜3ヶ月前に通知が来るように設定しておけば、余裕を持って業者選びや予約ができます。「車検 〇〇(車種名)」といったタイトルで、満了日を最終期限として登録し、その2ヶ月前に通知を設定するのがおすすめです。これにより、忙しい毎日の中でも車検の準備を計画的に進められます。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺スマホのカレンダーに「車検満了日+通知設定」を登録しておけば安心です!すぐに行いましょう!
- 車検証が最も確実な情報源。アプリで確認もOK。
- フロントガラスの車検シールでも簡単に確認できる。
- スマホリマインダーを使えば、うっかり忘れを防げる。
【Q&A】車検期間にまつわるよくある質問
![QA車検期間にまつわるよくある質問 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/QA車検期間にまつわるよくある質問-1024x683.jpg)
最後に、車検の期間に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
- 中古車を購入した場合の車検期間はどうなる?
-
中古車を購入した場合、車検の有効期間は前の所有者から引き継がれます。そのため、購入する車両によって残りの期間はバラバラです。「車検残あり」の車なら、車検証に記載された満了日までそのまま乗ることができます。一方、「車検なし」や「車検整備付」として販売されている車は、購入時に新しく2年間の車検を取得してから納車されるのが一般的です。
- 車検期間の延長はできる?
-
原則として、個人的な理由で車検の有効期間を延長することはできません。法律で定められた期間内に必ず更新する必要があります。ただし、大規模な自然災害など、国が指定する特定の状況下においては、特例として有効期間が延長される措置が取られることがあります。過去には、豪雨災害や感染症拡大の影響で延長措置が発表された例があります。
- 車検が受けられない期間はある?
-
基本的に、整備工場が営業していればいつでも車検を受けることは可能です。ただし、年末年始やゴールデンウィーク、お盆休みなどの長期休暇は、多くのディーラーや整備工場が休業するため、その期間は避けた方が賢明です。また、土日や祝日は混み合うことが多いため、平日に予約する方がスムーズに進む場合があります。特に年度末の3月は非常に混雑するため、早めの予約を心がけましょう。
まとめ
![まとめ - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/まとめ-10-1024x683.jpg)
今回は、車の種類ごとの車検期間から、2025年の法改正、年数と費用の関係、車検切れのリスクまで、幅広く解説しました。
- 自家用車は初回3年、以降は2年ごと。10年超えても変わりません。
- 2025年4月から、車検は満了日の「2ヶ月前」から受けられるようになります。
- 13年を超えると自動車重量税などが高くなるため、費用が増加する傾向にあります。
- 車検切れでの走行は「免許停止」を含む厳しい罰則の対象です。
車検は安全なカーライフに欠かせない大切な制度です。まずはご自身の愛車の車検証や車検シールを確認し、満了日を把握することから始めましょう。この記事が、あなたのスマートで安心なカーライフの一助となれば幸いです。
![HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](https://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/cc3d9ca1-c88b-463e-af8f-67dd29cc5449.png)