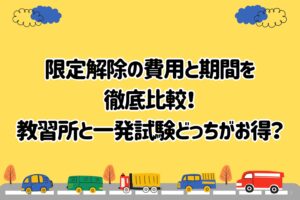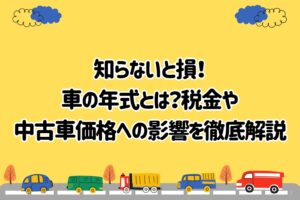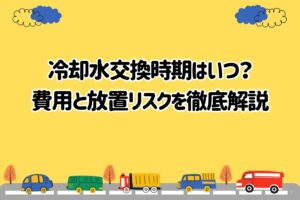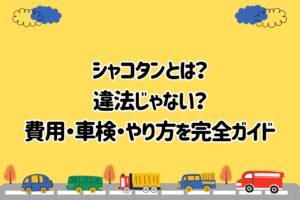「親から車を譲り受けることになったけど、手続きが複雑そうで何から手をつければいいかわからない…」
「平日は仕事で忙しいから、手続きは1日で完璧に終わらせたい!」
車の名義変更(移転登録)を前に、こんなお悩みを抱えていませんか?慣れない行政手続きは、必要書類が多く、どこで何をもらえばいいのか迷ってしまいますよね。書類に不備があって、何度も役所や運輸支局に足を運ぶことになったら…と考えると、うんざりしてしまうかもしれません。
ご安心ください。この記事を読めば、車の名義変更は、ポイントさえ押さえれば誰でも自分でスムーズに完了できます。
この記事では、普通自動車と軽自動車に分けて、名義変更に必要な書類を【印刷できるチェックリスト】でご紹介します。さらに、譲渡証明書や委任状の書き方見本、手続き当日の流れ、費用まで、図解を交えながら初心者の方にも分かりやすく徹底解説。
この記事をガイドブック代わりにすれば、窓口で慌てることなく、1日でスマートに手続きを終えられます。節約できた数万円で、新しいカー用品を揃えたり、家族で美味しい食事を楽しんだりするのも素敵ですね。さあ、一緒に準備を始めましょう!
- 普通車と軽自動車では、必要書類も手続き場所も大きく異なる。
- 名義変更は譲渡後15日以内に行わないと罰則対象。
- 印鑑証明や車庫証明など、発行期限に要注意(3ヶ月以内)。
- 業者に依頼すると2〜5万円かかるが、自分で行えば5,000円以下も可能。
- 書類の書き方・取得方法を事前に把握することで、当日ミスを防げる。
車の名義変更は、自分で行えば5,000円前後で完了できる手続きですが、必要書類や流れを知らないと大きな手間に。この記事では、普通車・軽自動車別に必要書類をわかりやすいチェックリストで紹介し、各書類の書き方から当日の流れ、費用、よくある質問までを網羅。この記事を使えば、平日1日で手続きをスムーズに終わらせられます!

まずはコレ!車の名義変更 必要書類チェックリスト
![まずはコレ車の名義変更 必要書類チェックリスト - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/まずはコレ車の名義変更-必要書類チェックリスト-1024x683.jpg)
車の名義変更を自分で行う場合、誰がどの書類を用意するのかを把握することが最初のステップです。ここでは、最も一般的な「個人間で車を譲渡・売買する場合」に必要な書類を、普通自動車と軽自動車に分けて一覧にまとめました。
ご自身の状況に合わせて、印刷してご活用ください。
【普通自動車】必要書類チェックリスト
| 用意する人 | 書類の種類 | チェック欄 |
|---|---|---|
| 旧所有者(譲る人) | 譲渡証明書(実印を押印) | □ |
| 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | □ | |
| 委任状(実印を押印) | □ | |
| 自動車検査証(車検証) | □ | |
| 自賠責保険証明書 | □ | |
| 自動車税(種別割)納税証明書 ※1 | □ | |
| リサイクル券 | □ | |
| 新所有者(受け取る人) | 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | □ |
| 実印 | □ | |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明)※2 | □ | |
| 当日、運輸支局で入手 | 手数料納付書 | – |
| 自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | – | |
| 申請書(OCRシート第1号様式) | – |
※1 納税証明書は、2023年1月から運輸支局で電子的に納税確認できるようになったため、原則不要です。ただし、システム化に対応できていない一部の自治体や、納税直後で情報が反映されていない場合は提示を求められることがあります。
※2 発行からおおむね1ヶ月以内のものが必要です。
【軽自動車】必要書類チェックリスト
| 用意する人 | 書類の種類 | チェック欄 |
|---|---|---|
| 旧所有者(譲る人) | 自動車検査証(車検証) | □ |
| 申請依頼書(認印を押印) | □ | |
| ナンバープレート(管轄が変わる場合) | □ | |
| 新所有者(受け取る人) | 住民票の写し or 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | □ |
| 認印 | □ | |
| 当日、軽自動車検査協会で入手 | 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) | – |
| 軽自動車税(種別割)申告書 | – |
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺事前にリストを印刷して、1つずつチェックしながら準備しましょう。忘れ物があると手続きが進まず、また平日休みを取ることになります。
- 普通車は「実印+印鑑証明」、軽自動車は「認印+住民票」でOK。
- 車庫証明が必要な地域と不要な地域があるため、地域ごとに確認を。
- 納税証明書は基本的に不要になっているが、念のため持参がおすすめ。
【普通自動車】必要書類の入手方法と書き方|徹底解説
![普通自動車必要書類の入手方法と書き方|徹底解説 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/普通自動車必要書類の入手方法と書き方|徹底解説-1024x683.jpg)
ここからは、普通自動車の名義変更に必要な書類について、1つずつ詳しく解説します。特に、自分で記入する必要がある書類は、見本を参考にしながら間違いのないように作成しましょう。
旧所有者(譲る人)が準備する書類
譲渡証明書
車の所有権が旧所有者から新所有者へ譲渡されたことを証明する、非常に重要な書類です。様式は国土交通省のウェブサイトからダウンロードできます。記入の際は、車検証に記載されている情報を正確に転記し、必ず旧所有者の実印を押印してください。書き損じた場合は、修正液を使わず、訂正箇所に二重線を引き、その上に訂正印(実印)を押します。
印鑑証明書
譲渡証明書と委任状に押された印鑑が、本人のものであることを証明する書類です。市区町村の役場で取得できます。発行から3ヶ月以内のものが必要ですので、手続きの直前に取得するようにしましょう。
委任状
名義変更の手続きを新所有者など代理人に任せる場合に必要です。旧所有者の実印を押印することで、手続きを委任した意思表示となります。様式は国土交通省のウェブサイトからダウンロード可能です。
自動車検査証(車検証)
車の基本情報が記載された証明書で、通常は車内に保管されています。手続きには有効期間内の原本が必要です。もし紛失した場合は、管轄の運輸支局で再交付の手続きを先に行う必要があります。
新所有者(受け取る人)が準備する書類
印鑑証明書
新所有者も、市区町村の役場で取得した発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。
実印
手続き当日に運輸支局で記入する申請書(OCRシート)に押印する際に必要となりますので、忘れずに持参しましょう。
自動車保管場所証明書(車庫証明)
車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で申請し、交付まで数日かかります。発行からおおむね1ヶ月以内のものが有効とされているため、名義変更の日程から逆算して早めに申請しておきましょう。
住所変更がある場合の追加書類
結婚や引越しなどで、車検証に記載されている旧所有者の氏名や住所が、現在の印鑑証明書の記載と異なる場合があります。その場合は、両者のつながりを証明するために、以下のいずれかの書類が追加で必要になります。
- 個人の場合:住民票(住所変更が1回の場合)または戸籍の附票(複数回転居している場合)
- 法人の場合:商業登記簿謄本など
これらの書類も発行から3ヶ月以内という有効期限がありますので注意してください。
当日、運輸支局で入手・記入する書類
以下の書類は、手続き当日に運輸支局(陸運局)の窓口で入手し、その場で記入します。
- 手数料納付書:登録手数料分の印紙を貼り付けるための用紙です。
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書:自動車の取得に伴う税金の申告に使用します。
- 申請書(OCRシート第1号様式):名義変更(移転登録)の申請本体となる書類です。
これらの書類は窓口に記入見本が用意されていることが多いので、参考にしながら落ち着いて記入しましょう。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺実印を押す書類はすべて「印鑑証明の印」と一致していないとNG!市役所での取得は計画的に。
- 譲渡証明書は実印と記入内容が重要、修正は訂正印で正しく。
- 委任状は「代理人による手続き」をする時に必須。
- 書類の有効期限(発行後3ヶ月以内)を過ぎると再取得になるので注意。
【軽自動車】必要書類の入手方法と書き方|普通車との違いも解説
![軽自動車必要書類の入手方法と書き方|普通車との違いも解説 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/軽自動車必要書類の入手方法と書き方|普通車との違いも解説-1024x683.jpg)
軽自動車の名義変更は、普通自動車に比べて手続きが簡素化されており、必要書類も少なくなります。一番大きな違いは、実印と印鑑証明書が不要で、認印で手続きが可能である点です。
旧所有者・新所有者がそれぞれ準備する書類
| 旧所有者(譲る人) | 新所有者(受け取る人) | |
|---|---|---|
| 必要な書類 | ・自動車検査証(車検証)の原本 ・申請依頼書(認印を押印) ・ナンバープレート ※管轄が変わる場合 | ・住民票の写し または 印鑑証明書の写し(発行後3ヶ月以内) ・認印 |
申請依頼書は、普通自動車の委任状にあたる書類です。新所有者が一人で手続きに行く場合、旧所有者から認印が押された申請依頼書を預かっておく必要があります。
新所有者が用意する住民票の写しは、マイナンバーが記載されていないものを用意しましょう。コピーでも手続き可能です。
当日、軽自動車検査協会で入手・記入する書類
普通自動車と同様に、手続き当日に窓口で入手・記入する書類があります。
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車税(種別割)申告書
普通自動車と軽自動車の名義変更の違い
普通自動車と軽自動車では、手続きの場所や必要なものが異なります。混同しないように、以下の表で違いをしっかり確認しておきましょう。
| 項目 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続き場所 | 新しい使用者の住所を管轄する運輸支局 | 新しい使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会 |
| 必要な印鑑 | 実印 | 認印 |
| 印鑑証明書 | 新旧所有者ともに原本が必要 | 不要(新所有者は住民票の写しでも可) |
| 車庫証明 | 事前に警察署で取得が必要 | 手続き後に届出が必要な地域が多い(不要な地域もある) |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合は、車を持ち込んで交換・封印が必要 | 管轄が変わる場合は、ナンバープレートを持参して返納・交付 |
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺「【軽自動車】必要書類の入手方法と書き方|普通車との違いも解説」
- 軽自動車は実印不要で簡単だが、「ナンバー管轄変更時」は注意。
- 新所有者の住民票はマイナンバーなしの写しを用意。
- 認印の押し忘れがよくあるミスなので要注意。
【実践編】車の名義変更手続きの流れ:5ステップ!
![実践編車の名義変更手続きの流れ5ステップ - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/実践編車の名義変更手続きの流れ5ステップ-1024x683.jpg)
必要書類が揃ったら、いよいよ手続き当日です。運輸支局(軽自動車検査協会)は平日しか開庁していないため、事前に流れを把握し、スムーズに進められるようにしましょう。
- Step1:必要書類の準備
この記事のチェックリストを活用し、前日までにすべての書類が揃っているか最終確認します。特に印鑑証明書や住民票などの有効期限は必ずチェックしてください。 - Step2:管轄の運輸支局(または軽自動車検査協会)へ
自分の新しい住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局へ向かいます。管轄がわからない場合は、国土交通省のウェブサイトで確認できます。月末や年度末は大変混み合うため、時間に余裕を持って行動しましょう。
▼国土交通省公式サイト:全国運輸支局等のご案内
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/list/index.html - Step3:窓口で申請書類の作成・提出
運輸支局に到着したら、まず案内窓口で名義変更(移転登録)の旨を伝え、手数料納付書、申請書、税申告書を受け取ります。印紙を購入して手数料納付書に貼り付け、すべての書類に必要事項を記入します。記入見本が置いてあるので、落ち着いて確認しながら書き進めましょう。記入が終わったら、すべての書類を揃えて申請窓口に提出します。 - Step4:新しい車検証の交付
書類に不備がなければ、名前が呼ばれ、新しい所有者の名前が記載された車検証が交付されます。記載内容に間違いがないか、その場で必ず確認してください。 - Step5:税金の申告とナンバープレートの交換
隣接する自動車税事務所で、自動車税(環境性能割・種別割)の申告手続きを行います。その後、管轄が変更になる場合は、古いナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを購入・取り付けます。普通自動車の場合は、係員に車台番号を確認してもらい、リアのナンバープレートに「封印」をしてもらって、すべての手続きが完了です。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺運輸支局は午前中が比較的空いています。早めに行動して、余裕を持ちましょう。
- 書類準備が8割。前日までにすべてのチェックを終えておく。
- 書類記入は窓口の見本を確認すれば迷わず進められる。
- ナンバー変更がある場合、普通車は「封印」作業があるため、車で行く必要がある。
車の名義変更にかかる費用はいくら?自分でやる場合 vs 業者依頼
![車の名義変更にかかる費用はいくら自分でやる場合 vs 業者依頼 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/車の名義変更にかかる費用はいくら自分でやる場合-vs-業者依頼-1024x683.jpg)
名義変更にかかる費用は、自分で行うか、業者に依頼するかで大きく変わります。
自分で手続きする場合の費用内訳
自分で行う場合、費用は法定手数料や書類発行手数料などの実費のみで済みます。
| 項目 | 費用(目安) |
|---|---|
| 移転登録手数料(印紙代) | 500円 |
| 車庫証明取得費用(証紙代) | 2,500円~3,000円 |
| ナンバープレート代 | 約1,500円~2,000円 ※管轄変更時 |
| 書類発行手数料(住民票など) | 1通 300円程度 |
| 合計 | 約4,800円~5,800円 |
この他に、車両によっては自動車税(環境性能割)が課税される場合があります。これは車の燃費性能などに応じて税率が変わるもので、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
業者に依頼する場合の費用相場
平日に時間が取れない方や手続きに不安がある方は、ディーラーや行政書士に代行を依頼することもできます。
| 依頼先 | 代行手数料の相場(実費別途) | 特徴 |
|---|---|---|
| ディーラー | 20,000円~50,000円 | 安心感が高いが、費用は高め。 |
| 中古車販売店 | 10,000円~30,000円 | 車の購入と同時に依頼するとスムーズ。 |
| 行政書士 | 10,000円~20,000円 | 書類作成のプロ。複雑なケースにも対応可能。 |
代行を依頼すると手間は省けますが、数万円の費用がかかります。費用を抑えたい方は、ぜひご自身での手続きにチャレンジしてみてください。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺平日に時間を確保できるなら、この記事を見ながらの「セルフ手続き」が一番コスパ良し!
- 自分で手続きすれば5,000円前後で済む。
- 業者に頼むと2〜5万円ほど必要だが、時間と手間はかからない。
- 環境性能割の課税対象かどうかで費用が変動する。
車の名義変更 Q&A|よくある疑問とトラブル解決策
![車の名義変更 QA|よくある疑問とトラブル解決策 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/車の名義変更-QA|よくある疑問とトラブル解決策-1024x683.jpg)
最後に、名義変更に関するよくある質問にお答えします。
- 名義変更はいつまでにやらないといけない?放置するとどうなる?
-
道路運送車両法により、所有者が変わった日から15日以内に手続きを行うことが義務付けられています。怠ると50万円以下の罰金が科せられる可能性があるほか、自動車税の納税通知が旧所有者に届き続ける、事故の際に保険手続きが複雑になるなどのトラブルの原因になります。
- 平日に休みが取れない!土日でも手続きできる?
-
残念ながら、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口は平日のみの受付となります。どうしてもご自身で行けない場合は、家族などを代理人として委任状(軽自動車は申請依頼書)を持たせて手続きを依頼するか、行政書士などの代行サービスを利用する方法があります。
- 親子間の譲渡でも贈与税はかかる?
-
親子間など無償で車を譲り受けた場合は「贈与」とみなされ、車の時価額によっては贈与税の対象となる可能性があります。ただし、年間110万円の基礎控除があるため、ほとんどの中古車の場合は非課税で済むことが多いです。ただし、高級車や新車同様の車を譲り受ける場合は注意が必要です。
- ローンが残っている車でも名義変更できる?
-
ローンが残っている車は、所有者がローン会社やディーラーになっている場合(所有権留保)がほとんどです。この場合、ローンを完済して所有権を自分に移す「所有権解除」の手続きをしないと、名義変更はできません。まずはローン会社に連絡して、完済手続きについて確認しましょう。
- 相続で車を譲り受けた場合、必要書類は違う?
-
はい、異なります。通常の譲渡とは違い、亡くなった所有者(被相続人)の戸籍謄本(除籍謄本)や、誰が車を相続するのかを証明する遺産分割協議書など、相続を証明するための書類が追加で必要になります。相続人が複数いる場合は手続きが複雑になるため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
![まとめ - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/まとめ-9-1024x683.jpg)
車の名義変更は、事前に必要書類をしっかり準備すれば、決して難しい手続きではありません。
- 普通自動車と軽自動車で必要書類や手続き場所が異なることを理解する。
- この記事のチェックリストを活用し、書類の漏れや不備を防ぐ。
- 譲渡証明書や委任状は、書き方見本を参考に正確に記入する。
- 手続きは平日の日中しかできないため、時間に余裕を持って計画を立てる。
この記事を参考に万全の準備を整え、スムーズに手続きを完了させてください。名義変更が終わったら、最後に任意保険の契約者変更も忘れずに行い、新しい愛車とのカーライフを安心してスタートさせましょう。
![HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](https://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/cc3d9ca1-c88b-463e-af8f-67dd29cc5449.png)