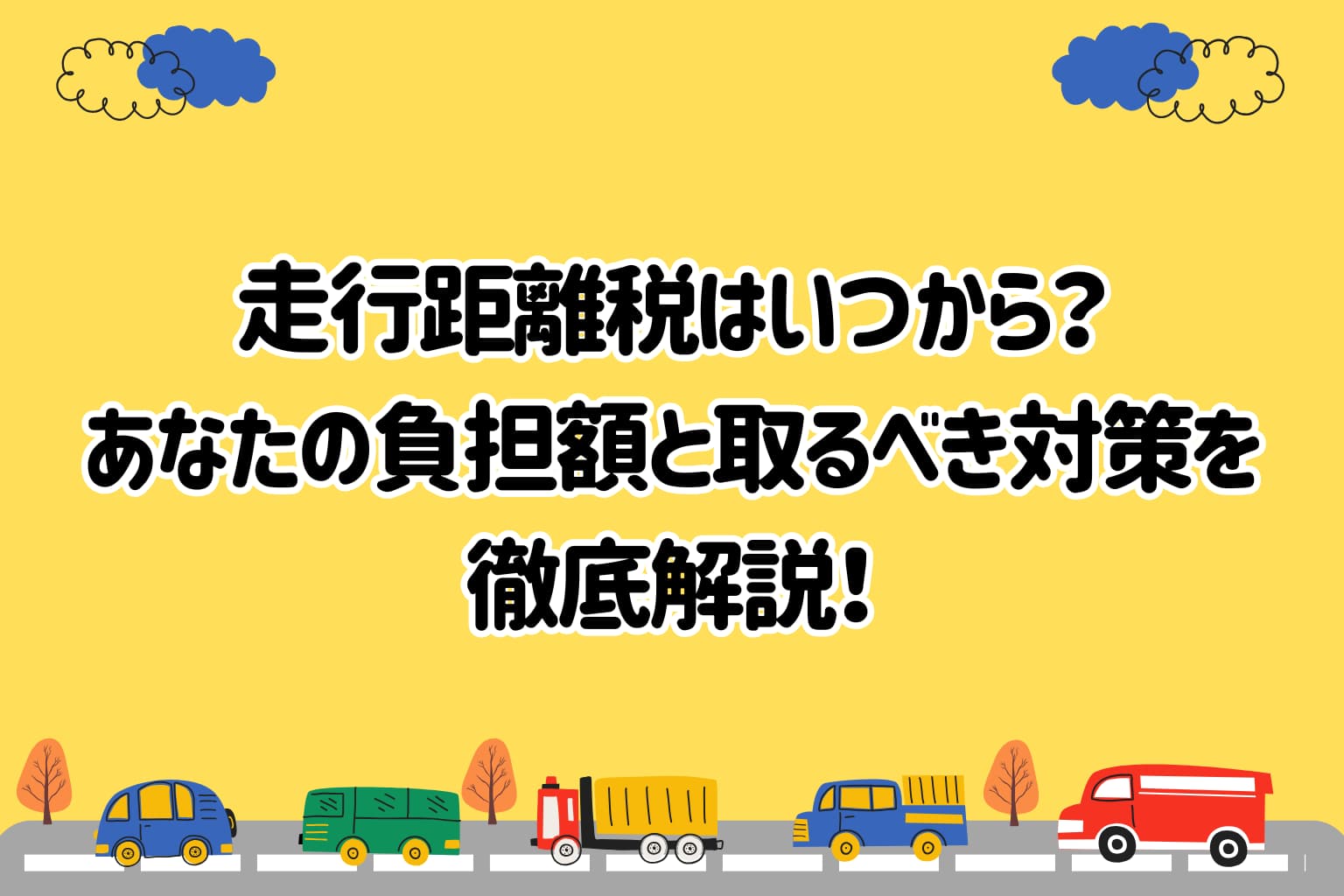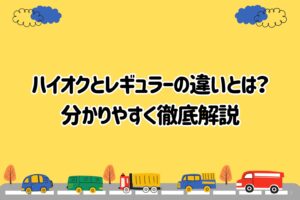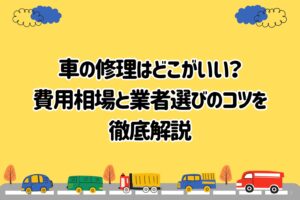「最近ニュースで『走行距離税』という言葉を聞くけど、一体どんな税金なんだろう?」
「通勤や仕事で毎日たくさん車に乗るから、もし導入されたら自分の税金はいくら増えるんだろう?」
地方にお住まいで、お仕事や生活に車が欠かせない方ほど、このような漠然とした不安を感じているのではないでしょうか。ガソリン代や物価が上がる中、これ以上の負担増は避けたいのが本音ですよね。
ご安心ください。この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消するために、走行距離税(走行距離課税)の全てを網羅的に、そしてどこよりも分かりやすく解説します。
現時点での結論を先にお伝えすると、走行距離税の導入時期はまだ決まっていません。しかし、政府内での議論は着実に進んでいます。将来の家計への影響を最小限に抑えるためにも、制度を正しく理解し、今から賢く備えることが重要です。
- 走行距離税は「距離ベースの公平課税」で、車の利用実態に応じて税負担が変化します。
- EV普及によりガソリン税収が減少しており、新たな財源として検討中。
- 負担の大小は走行距離次第で、都市部の人より地方・長距離ドライバーの負担が増加。
- プライバシーや地方格差といった課題があり、導入には丁寧な制度設計が必要。
- 対策は今から可能で、エコドライブや車種選びの見直しなどで備えられます。
走行距離税とは、車が走った距離に応じて課税される新しい税金で、EV(電気自動車)の普及によるガソリン税の減少を補うために検討が進んでいます。まだ導入時期は決まっていませんが、将来的な可能性は高く、特に車を多く使う地方在住者や運送業者には大きな影響があります。この記事では、制度の概要、メリット・デメリット、税額シミュレーション、導入に向けた対策までをわかりやすく解説しています。

【理解編】走行距離税とは?制度の全体像をわかりやすく解説
![走行距離税とは制度の全体像をわかりやすく解説 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/走行距離税とは制度の全体像をわかりやすく解説-1024x683.jpg)
まずは、走行距離税がどのような制度なのか、その基本から見ていきましょう。なぜ今この税金が注目されているのか、その背景やメリット・デメリットを理解することで、全体像がクリアになります。
走行距離税(走行距離課税)の基本的な仕組み
走行距離税とは、その名の通り「自動車が走った距離に応じて課税される」税金です。現在の自動車税が主に排気量で決まるのに対し、走行距離税は「どれだけ道路を利用したか」を基準にします。
この制度の基本的な考え方は、「道路という社会インフラを利用した分だけ、その維持・管理費用を負担してもらう」というものです。つまり、車をたくさん利用する人ほど多くの税金を納め、あまり利用しない人は負担が軽くなる、という公平性を目指した仕組みと言えます。この公平性の観点から、電気自動車(EV)などガソリンを使わない車も課税対象に含まれるのが大きな特徴です。
なぜ今、走行距離税が検討されているのか?3つの背景
走行距離税が本格的に議論され始めた背景には、大きく分けて3つの理由があります。
- EV(電気自動車)の普及によるガソリン税収の減少
最も大きな理由がこれです。現在、道路の維持・管理費用の主な財源は、ガソリンにかかる「ガソリン税」です。しかし、EVやハイブリッド車の普及によりガソリンの消費量が減り、将来的に税収が大幅に落ち込むことが確実視されています。経済産業省の試算では、2030年にはガソリン税収が最大1兆円減少する可能性も指摘されています。この減少分を補う新たな財源として、走行距離税が注目されているのです。 - 税負担の公平性の確保
現行の税制では、ガソリンを使わないEVユーザーは道路の維持費をほとんど負担していません。一方で、同じように道路を利用しているガソリン車ユーザーはガソリン税を払い続けています。この「利用しているのに負担しない」という不公平感を是正し、燃料の種類に関わらず、道路の利用実態に応じて公平に負担を求めるべきだという考え方が強まっています。 - 若者の車離れと税収の安定化
都市部を中心に、車を所有しない若者が増えています。これにより、排気量に応じて課税される自動車税(種別割)の税収も先細りが懸念されています。走行距離税は、車をあまり使わない人にとっては税負担が軽くなる可能性があるため、車の所有のハードルを下げる効果も期待されています。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺「公平で持続可能な制度」に変わる可能性があるため、内容を理解して冷静に受け止めましょう。
- 課税の基準が「排気量」から「実際の利用量」へと変化する画期的な仕組み。
- EVや燃費の良い車にも公平に負担を求める流れが加速。
- 環境・インフラ維持の両面で現行制度の限界を補う狙いがある。
メリットとデメリット:本当に得になるの?
![メリットとデメリット本当に得になるの - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/メリットとデメリット本当に得になるの-1024x683.jpg)
走行距離税のメリット:公平な負担と環境への配慮
走行距離税の導入には、いくつかのメリットが期待されています。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 公平性の向上 | 燃料の種類(ガソリン、軽油、電気など)に関わらず、道路の利用量に応じて課税されるため、ユーザー間の税負担が公平になります。 |
| 税収の安定化 | EVが普及しても、走行する限りは課税できるため、道路インフラを維持するための財源を安定的に確保できます。 |
| 環境負荷の低減 | 走行距離が短いほど税負担が軽くなるため、不要な車の利用を抑制するインセンティブが働きます。結果としてCO2排出量の削減や交通渋滞の緩和につながる可能性があります。 |
| 車の保有しやすさ | あまり車に乗らない人(サンデードライバーなど)にとっては、現在の自動車税よりも負担が減る可能性があります。これにより、車を保有するハードルが下がるかもしれません。 |
走行距離税のデメリットと懸念点:地方格差やプライバシー問題
一方で、走行距離税には多くのデメリットや解決すべき課題も指摘されています。特に、車が生活必需品である地方在住者にとっては、切実な問題です。
| デメリット・懸念点 | 詳細 |
|---|---|
| 地方在住者の負担増 | 公共交通機関が乏しく、通勤や買い物などで長距離移動が必須な地方の住民は、都市部の住民に比べて走行距離が長くなるため、税負担が著しく重くなる恐れがあります。地方いじめとも言える不公平感を生む可能性があります。 |
| 物流・運送業への影響 | 長距離を走るトラックなどが主な輸送手段である物流業界では、コストが大幅に増加します。このコスト増は運賃に転嫁され、最終的に私たちの購入する商品の価格が上がることにつながりかねません。 |
| プライバシー侵害の懸念 | 走行距離を正確に把握するためには、GPSなどの追跡技術が必要となります。これにより、個人の移動履歴という非常にプライベートな情報が国に収集・管理されることになり、プライバシー侵害のリスクが大きな課題となります。 |
| 観光・レジャー産業への悪影響 | 税負担を気にして、長距離のドライブや旅行を控える人が増える可能性があります。これは、観光地や関連産業にとって大きな打撃となることが懸念されます。 |
【比較表】現行の自動車税制との違いは?
走行距離税と現行の主な自動車関連税の違いをまとめると、以下のようになります。
| 税の種類 | 課税基準 | 特徴 |
|---|---|---|
| 走行距離税(検討中) | 走行距離 | ・道路の利用量に応じた負担・EVも課税対象 |
| 自動車税(種別割) | 総排気量 | ・車の所有に対して課税・毎年支払う地方税 |
| 自動車重量税 | 車両重量 | ・車検時に支払う国税・重量が重いほど高くなる |
| ガソリン税(揮発油税など) | ガソリンの量 | ・給油時に支払う国税・道路の財源となっている |
| 環境性能割 | 環境性能 | ・車の購入時に支払う地方税・燃費が良いほど安くなる |
このように、走行距離税は「所有」から「利用」へと課税の基準を大きく変えるものであり、導入されれば日本の自動車税制の大きな転換点となります。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺長距離移動が多い方は、負担増の可能性を前提に家計の見直しを検討しましょう。
- 不必要な車の使用抑制 → CO₂削減や渋滞緩和に貢献。
- 地方と都市の移動ニーズの差が格差として現れやすい。
- 税の透明性と納得感を高めるにはプライバシー配慮が不可欠。
【Q&A】走行距離税はいつから?いくらになる?気になる疑問に回答
![QA走行距離税はいつからいくらになる気になる疑問に回答 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/QA走行距離税はいつからいくらになる気になる疑問に回答-1024x683.jpg)
制度の概要がわかったところで、次に皆さんが最も気になるであろう具体的な疑問にお答えしていきます。
- 走行距離税はいつから導入される?2025年ではない?
-
現時点(2024年)で、走行距離税の具体的な導入時期は決まっていません。
一部で「2025年度の税制改正で議論される」といった報道がありましたが、これはあくまで議論が本格化する可能性を示唆したもので、すぐに導入が決まるわけではありません。税制の大きな変更には、国民的な議論や法整備、システムの構築などが必要で、数年単位の時間がかかると考えられます。ただし、政府税制調査会などでは継続的に検討課題として挙げられており、中長期的な導入を目指していることは間違いありません。 - 税額は1kmあたりいくらになる?
-
税率についても、まだ具体的な金額は示されていません。
もし仮に、現在のガソリン税収(約5兆円)を走行距離税だけで賄うと仮定すると、日本の自動車の総走行距離(約6,000億km)で割ることで、単純計算上の税率を推測することは可能です。この場合、1kmあたり約8円となりますが、これはあくまで机上の計算です。
実際には、車種(軽自動車、普通車、大型トラックなど)や、環境性能、利用する地域(都市部か地方か)などによって税率が変わる可能性があります。例えば、「地方在住者には税率を低くする」「EVは税率を優遇する」といった調整が議論されることになるでしょう。
- ガソリン税や自動車税との二重課税になる?
-
多くの人が懸念しているのが「二重課税」の問題です。もし走行距離税が導入されてもガソリン税や自動車税がそのまま残れば、ユーザーの負担は過重になります。
この点について、政府の議論では、走行距離税を導入する場合は既存の税金(特にガソリン税や自動車税)を廃止または減額する方向で検討が進められています。例えば、「ガソリン税を廃止して走行距離税に一本化する」「自動車税を大幅に引き下げ、その分を走行距離税で補う」といった形が考えられます。国民の理解を得るためには、二重課税とならないような制度設計が不可欠です。
- 走行距離はどうやって把握するの?プライバシーは大丈夫?
-
走行距離を正確に把握する方法として、主に3つの技術が検討されていますが、それぞれに課題があります。
把握方法 メリット デメリット・課題 GPS追跡 ・最も正確に走行距離を把握できる・道路の種類や時間帯別の課税も可能 ・プライバシー侵害の懸念が最も大きい・全車両への搭載コストが高い 車載器(OBD2ポート利用など) ・GPSよりはプライバシーへの懸念が低い・比較的正確なデータを自動送信できる ・車載器の設置コストがかかる・データの改ざん防止技術が必要 オドメーター(走行距離計) ・導入コストが最も低い ・自己申告制のため、改ざんのリスクがある・車検時などの定期的な確認が必要 どの方法を採用するにしても、プライバシー保護は最大の課題です。走行データを暗号化したり、個人が特定できないように匿名化したりといった厳格なデータ管理体制の構築が必須となります。国民の不安を払拭できなければ、制度の導入は難しいでしょう。
海外ではどうなってる?世界の走行距離税導入事例
![海外ではどうなってる世界の走行距離税導入事例 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/海外ではどうなってる世界の走行距離税導入事例-1024x683.jpg)
走行距離税は、日本だけでなく世界各国で検討・導入されています。海外の事例を知ることは、日本の未来を考える上で非常に参考になります。
【成功事例】ニュージーランドの「道路利用車料(RUC)」
ニュージーランドでは「RUC (Road User Charges)」という制度が古くから導入されています。主にディーゼル車や大型車両が対象で、最近ではEVも対象に加えられました。この制度の特徴は、走行距離を予測して料金を事前購入する点です。ドライバーは1,000km単位でライセンスを購入し、そのステッカーを車に貼り付けます。これにより、燃料に課税されていない車両からも公平に道路維持費を徴収することに成功しています。
【技術先進事例】ドイツの大型トラック向け「LKW-Maut」
ドイツでは、12トン以上の大型トラックを対象にGPS技術を活用した走行距離課金制度「LKW-Maut」を導入しています。車載器が高速道路の走行距離を自動で計測し、料金を徴収する仕組みです。税収は道路整備に充てられており、インフラ維持の財源確保に貢献しています。対象が事業用の大型車に限定されているため、国民的な反発は比較的小さいようです。
【任意参加プログラム】アメリカ・オレゴン州の「OReGO」
アメリカのオレゴン州では、「OReGO」という任意参加型の走行距離課金プログラムが実施されています。参加者はガソリン税を支払う代わりに、走行距離に応じて1マイルあたり約1.9セントを支払います。走行距離の記録方法は、GPS機能付きの車載器や、GPSなしの装置など、プライバシーへの配慮から複数の選択肢が用意されているのが特徴です。しかし、任意参加のため普及率が低いという課題があります。
海外事例から学ぶ日本の課題
これらの海外事例から、日本が走行距離税を導入する上での課題が見えてきます。
- 国民の理解と合意形成:特に乗用車全体を対象とする場合、ニュージーランドやアメリカの事例のように、公平性やプライバシー保護について丁寧な説明と国民の合意が不可欠です。
- 地域差への配慮:日本の国土は多様であり、特に地方の生活実態に合わせた制度設計(税率の調整など)が重要になります。
- 技術とコストのバランス:ドイツのような高度なシステムは正確ですがコストがかかります。プライバシー保護とコスト、精度のバランスをどう取るかが鍵となります。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺「海外の仕組み=正解」ではないので、日本独自の課題に注目を。
- ニュージーランドやドイツなどは導入実績があり参考になる。
- プライバシーに配慮した「選べる方式」が日本にも必要。
- 国民の合意形成なしでは制度の定着は難しい。
【影響編】あなたの負担はいくら増える?モデルケース別税額シミュレーション
![影響編あなたの負担はいくら増えるモデルケース別税額シミュレーション - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/影響編あなたの負担はいくら増えるモデルケース別税額シミュレーション-1024x683.jpg)
ここからは、もし走行距離税が導入された場合、あなたの家計にどのような影響が出るのか、具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。
※以下のシミュレーションは、あくまで仮定に基づく試算です。実際の税額とは異なります。
シミュレーションの前提条件
- 走行距離税の税率を1kmあたり5円と仮定します。
- 走行距離税の導入に伴い、現在の自動車税(種別割)とガソリン税(1Lあたり約54円)は廃止されるものとします。
ケース1:地方在住の営業職・鈴木さん(年間30,000km)
今回の記事のペルソナである鈴木さんのケースです。
- 車種:普通乗用車(排気量1.8L、燃費15km/L)
- 年間走行距離:30,000km
【現行の税負担】
- 自動車税:36,000円/年
- ガソリン税:(30,000km ÷ 15km/L) × 54円/L = 108,000円/年
- 合計:144,000円/年
【走行距離税導入後】
- 走行距離税:30,000km × 5円/km = 150,000円/年
- 差額:+6,000円/年
このシミュレーションでは、鈴木さんのような長距離ドライバーの場合、年間で6,000円の負担増となりました。税率が1kmあたり6円になれば、負担増は年間36,000円にまで膨らみます。
ケース2:都市部在住のサンデードライバー(年間5,000km)
- 車種:コンパクトカー(排気量1.3L、燃費20km/L)
- 年間走行距離:5,000km
【現行の税負担】
- 自動車税:30,500円/年
- ガソリン税:(5,000km ÷ 20km/L) × 54円/L = 13,500円/年
- 合計:44,000円/年
【走行距離税導入後】
- 走行距離税:5,000km × 5円/km = 25,000円/年
- 差額:-19,000円/年
都市部に住み、週末にしか車に乗らないようなケースでは、年間で19,000円もの負担減となりました。あまり車に乗らない人にとっては、メリットが大きい制度と言えそうです。
ケース3:運送業の小型トラック(年間80,000km)
- 車種:小型トラック(ディーゼル車、燃費10km/L)
- 年間走行距離:80,000km
【現行の税負担(軽油引取税で計算)】
- 自動車税:11,500円/年
- 軽油引取税:(80,000km ÷ 10km/L) × 32.1円/L = 256,800円/年
- 合計:268,300円/年
【走行距離税導入後】
- 走行距離税:80,000km × 5円/km = 400,000円/年
- 差額:+131,700円/年
運送業者の負担は非常に大きくなります。このケースでは年間13万円以上の大幅なコスト増となり、これが運賃に反映されることで、私たちの生活にも影響が及ぶ可能性が高いことがわかります。
シミュレーション結果からわかること:走行距離が長いほど負担増
このシミュレーションから、走行距離税は「あまり乗らない人には減税、たくさん乗る人には増税」となる可能性が高いことが明確になりました。特に、鈴木さんのような地方の営業職の方や、運送業に携わる方にとっては、家計や経営に直接的な影響を与える深刻な問題となり得ます。だからこそ、今から対策を考えておくことが重要なのです。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺自分の走行距離を1年分見直すだけで、影響の予測が可能になります。
- 年間走行距離が多い人ほど、走行距離税で負担増。
- 都市部のサンデードライバーはむしろ減税の可能性あり。
- 運送業は業界全体に影響 → 最終的に物価へ跳ね返る可能性。
【対策編】家計へのダメージを最小限に!今からできる超・具体的ロードマップ
![今からできる超具体的ロードマップ - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/今からできる超具体的ロードマップ-1024x683.jpg)
走行距離税の導入はまだ先の話ですが、将来の負担増に備えて今からできることはたくさんあります。ここでは、「短期」「中期」「長期」の3つの視点で、具体的な対策ロードマップを提示します。
【短期対策】明日からできる!走行距離を減らす3つの工夫
まずは、お金をかけずに今すぐ始められることから取り組みましょう。
- エコドライブを徹底する
「急」のつく運転(急発進、急加速、急ブレーキ)をやめるだけで、燃費は大きく向上します。車間距離を十分に保ち、先の信号を予測してアクセルを早めに離す「予測運転」を心がけましょう。これは安全運転にもつながります。 - 不要なアイドリングをやめる
荷物の積み下ろしや待ち合わせの際のアイドリングは、無駄な燃料を消費します。10分間のアイドリングで約130ccの燃料を消費すると言われています。こまめにエンジンを止める習慣をつけましょう。 - 日々のメンテナンスを欠かさない
タイヤの空気圧が適正でないと、燃費が悪化します。月に一度はガソリンスタンドなどで空気圧をチェックしましょう。また、エンジンオイルの定期的な交換や、不要な荷物を車から降ろして車体を軽くすることも燃費向上に効果的です。
【中期対策】ライフスタイルの見直しと代替手段の活用
次に、少し視点を広げて、車との付き合い方そのものを見直してみましょう。
- 移動手段の最適化
「ちょっとそこまで」の買い物に、毎回車を使っていませんか?天気の良い日は自転車を使ったり、歩いたりすることで、走行距離を減らせるだけでなく健康増進にもつながります。 - 公共交通機関やカーシェアの活用
通勤ルートにバスや電車が利用できる区間があれば、パークアンドライド(駅近くの駐車場に車を停めて公共交通機関を利用する方法)を検討してみましょう。また、セカンドカーの利用頻度が低い場合は、思い切って手放し、必要な時だけカーシェアを利用するのも賢い選択です。 - テレワークの活用
もしお仕事で可能であれば、週に1〜2日でもテレワークを導入することで、通勤にかかる走行距離を大幅に削減できます。会社に制度がないか確認したり、導入を働きかけてみるのも一つの手です。
【長期対策】将来を見据えた賢い車の選び方
数年先を見据えて、次に乗る車について考えておくことも重要です。
- 燃費性能を最優先に
次に車を買い替える際は、デザインや走行性能だけでなく、燃費性能を最も重要な基準の一つとして考えましょう。ハイブリッド車(HV)は、ガソリン車に比べて燃費が良く、走行距離税導入後もガソリン代の節約効果は続きます。 - ライフスタイルに合った車格を選ぶ
家族構成や用途に対して、過度に大きな車に乗っていませんか?例えば、子供が独立した後は、ミニバンからコンパクトカーに乗り換えるなど、ライフスタイルの変化に合わせて車をダウンサイジングすることも、維持費全体の削減につながります。
EV・PHEVへの買い替えは本当に「得」なのか?
走行距離税はEVも対象になるため、「EVに買い替えても意味がない」と考えるのは早計です。税率がガソリン車より優遇される可能性は十分にあります。
ただし、重要なのは税金だけでなくトータルコストで判断することです。EVは車両価格が高く、自宅に充電設備を設置する費用もかかります。また、長距離移動が多い場合は、充電スポットの数や充電時間も考慮に入れる必要があります。走行距離税の議論が進み、EVへの税率優遇などが明確になってから、自身のライフスタイルや走行距離と照らし合わせて、慎重に判断するのが得策です。
今後の動向と最新情報のキャッチアップ方法
走行距離税に関する議論は、今後も続いていきます。不確かな情報に惑わされず、正しい情報を得ることが大切です。
走行距離税の議論はどこで進められている?
走行距離税に関する本格的な議論は、主に政府税制調査会で行われます。ここで専門家や有識者が中長期的な税金のあり方を議論し、答申をまとめます。その答申をもとに、年末に与党(自民党・公明党)が「与党税制改正大綱」として翌年度の税制改正の具体的な方針を決定します。このプロセスを覚えておくと、ニュースの流れが理解しやすくなります。
信頼できる情報源リスト
最新かつ正確な情報を得るためには、以下の一次情報をチェックすることをおすすめします。
- 財務省「税制調査会」のページ:議事録や配布資料が公開されており、議論の具体的な内容を確認できます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/index.html - 国土交通省の関連ページ:自動車関連の税制や道路政策に関する情報が掲載されます。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html - 大手新聞社や通信社のニュースサイト:税制改正大綱が発表される年末(12月中旬頃)には、詳しい解説記事が出ます。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺将来の「走行コスト」を考えて、車の買い替えタイミングと条件を見直しましょう。
- 短期:エコ運転・メンテナンス・アイドリングストップで燃費改善。
- 中期:カーシェアや公共交通の活用でライフスタイル見直し。
- 長期:次に買う車は「燃費・サイズ・使用頻度」で選ぶべき。
まとめ:走行距離税の不安を解消し、賢い未来へ備えよう
![まとめ走行距離税の不安を解消し賢い未来へ備えよう - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/まとめ走行距離税の不安を解消し賢い未来へ備えよう-1024x683.jpg)
今回は、走行距離税について、その仕組みから具体的なシミュレーション、そして今からできる対策までを徹底的に解説しました。
重要なポイントを振り返ります。
- 走行距離税は「走った分だけ課税」される公平性を目指した税金で、EV普及による税収減を補う目的がある。
- 導入時期や税額は未定だが、中長期的な導入に向けた議論は進んでいる。
- 地方在住者や運送業など、長距離を走るユーザーほど負担が増える可能性が高い。
- 導入に備え、日々の運転の見直し(短期)からライフスタイルの最適化(中期)、将来の車選び(長期)まで、今からできる対策は多い。
走行距離税のニュースは、私たちドライバーにとって不安なものかもしれません。しかし、制度を正しく理解し、その背景にある課題を知ることで、漠然とした不安は「具体的な備え」へと変えることができます。この記事が、あなたの不安を解消し、賢く未来に備えるための一助となれば幸いです。
![HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](https://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/cc3d9ca1-c88b-463e-af8f-67dd29cc5449.png)