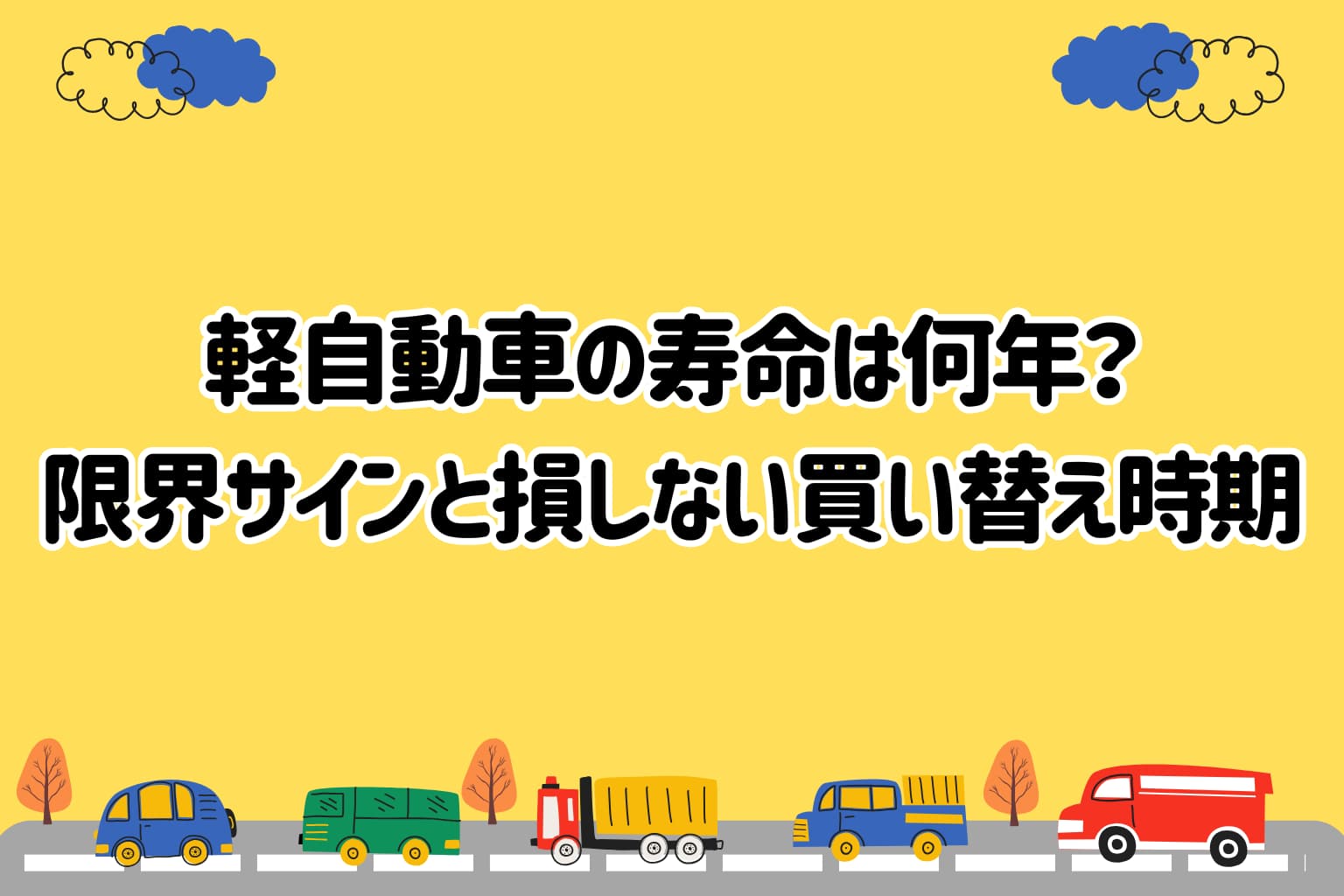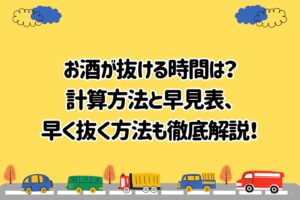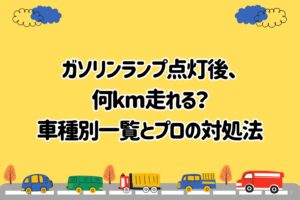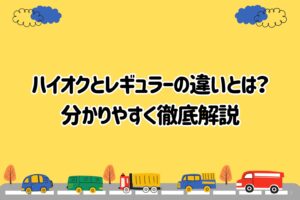「うちの軽自動車、毎日頑張ってくれているけど、あと何年くらい安全に乗れるんだろう…」
「走行距離が10万kmを超えたら、やっぱり買い替えないと危ないのかな?」
毎日の通勤やお子様の送迎、買い物に欠かせない軽自動車。長年連れ添った愛車だからこそ、そんな不安や疑問がふと頭をよぎりますよね。特に、坂道で少しパワーが落ちたように感じたり、小さな異音が気になったりすると、次の車検を通すべきか、大きな出費になる前に買い替えるべきか、悩んでしまうお気持ちは非常によくわかります。
結論からお伝えすると、近年の軽自動車の寿命は、私たちが思っている以上に長いです。軽自動車検査協会の最新データによれば、軽自動車の平均使用年数は16.21年にも達しています。これは、昔よく言われた「10年10万km」という常識が、もはや過去のものであることを示しています。
この記事では、あなたの軽自動車の本当の寿命を見極めるための具体的な判断基準から、故障前に現れる危険な「限界サイン」、そして家計に最も優しい損しない買い替えタイミングまで、専門的な内容を誰にでもわかるように徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの愛車にとって最適な「乗り続ける」か「買い替える」かの判断が、自信を持ってできるようになっているはずです。
- 寿命の平均は16.21年で、10年10万kmはもう古い常識。
- 走行距離20万km超も可能だが、部品交換などの整備が重要。
- 車の状態こそ最重要。年数や距離よりメンテナンスの質がカギ。
- 寿命のサインは5つ(エンジン異音、ブレーキ不調など)で早期発見が必要。
- 買い替えの好機は13年目・修理費増加・価値の下落前。
軽自動車の寿命は「10年10万km」が常識だった時代は終わり!今は16年以上乗れる車が当たり前です。寿命を判断するには、年数・走行距離・車両の状態の3つをチェックしましょう。エンジン異音やブレーキの効きが悪くなるなど、寿命が近づくサインにも要注意。買い替えのベストタイミングは「13年目の税金アップ」や「高額修理前」。まだ乗るなら、定期的なオイル交換と丁寧な運転で寿命を伸ばすことも可能です。
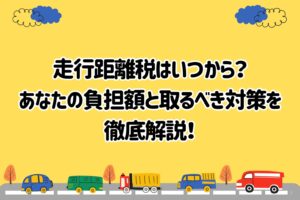
【結論】軽自動車の寿命は平均16.21年!本当の判断基準は3つ
![軽自動車の寿命は平均1621年本当の判断基準は3つ - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/軽自動車の寿命は平均1621年本当の判断基準は3つ-1024x683.jpg)
「軽自動車の寿命は10年10万km」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、これは一昔前の話です。自動車製造技術の飛躍的な向上により、現在の軽自動車は非常に頑丈で長持ちするようになりました。公的なデータもそれを裏付けています。本当の寿命を見極めるには、「年数」「走行距離」「車両状態」という3つの視点から総合的に判断することが大切です。
1. 年数で見る寿命:10年・10万kmはもう古い?
かつて軽自動車の寿命は10年が目安とされていましたが、これは過去の常識です。軽自動車検査協会が2024年に発表したデータによると、軽自動車(乗用)の平均使用年数は16.21年という結果が出ています。これは新車として登録されてから廃車になるまでの平均期間であり、多くの軽自動車が15年以上も活躍していることを示しています。
もちろん、これはあくまで平均値です。適切なメンテナンスを続けていれば20年以上乗り続けることも可能ですし、逆にメンテナンスを怠れば10年を待たずに寿命を迎えることもあります。年数はあくまで一つの目安と捉えましょう。
2. 走行距離で見る寿命:20万km超えも夢じゃない
走行距離も寿命を判断する重要な指標です。一般的に、年間走行距離の目安は約1万kmと言われています。走行距離が増えるほど、エンジンや足回りの部品は消耗していきます。
| 走行距離 | 主なメンテナンス・交換部品の目安 |
|---|---|
| 10万km | タイミングベルト、ウォーターポンプ、スパークプラグ、各種ゴム部品(ブッシュ類)など |
| 15万km | サスペンション、ブレーキ関連部品、オルタネーター(発電機)、ラジエーターなど |
| 20万km | エンジンやトランスミッション本体のオーバーホールまたは載せ替えを検討する時期 |
表を見ると、10万kmを超えると重要な部品の交換が必要になることがわかります。しかし、これらの基幹部品をしっかりと交換・整備すれば、20万kmを超えても安全に走行することは十分可能です。整備記録がしっかり残っており、10万kmのタイミングで適切な整備がされた中古車は、むしろ安心材料と考えることもできます。
3. 車両状態で見る寿命:年数や距離より重要
ここまで年数と走行距離について解説してきましたが、軽自動車の寿命を判断する上で最も重要なのは「現在の車両状態」です。たとえ年式が古くても、走行距離が長くても、定期的なメンテナンスが行き届いていれば車のコンディションは良好に保たれます。
逆に、年式が新しく走行距離が短くても、オイル交換を怠ったり、乱暴な運転を続けたりすれば、車はあっという間に傷んでしまいます。大切なのは、数字だけに惑わされず、愛車が発する「声」に耳を傾けることです。次の章では、その具体的な「声」、つまり寿命が近いことを知らせる危険な限界サインについて詳しく解説します。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺年式や走行距離だけで判断せず、整備履歴を見てプロに点検してもらいましょう。
- 製造技術が進化し、15〜20年乗れる車が一般的になっている。
- 年数・走行距離だけでなく「今の状態」を見ることが寿命判断の鍵。
- 維持コストや修理歴も総合的に評価することが大切。
【プロが警告】愛車の寿命が近い5つの限界サイン
![愛車の寿命が近い5つの限界サイン - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/愛車の寿命が近い5つの限界サイン-1024x683.jpg)
「最近、なんだか車の調子が悪い気がする…」その感覚は、愛車があなたに送っている重要なメッセージかもしれません。ここでは、プロの整備士が「これは危険」と判断する、寿命が近い5つの限界サインを解説します。これらのサインを見逃すと、突然の故障や高額な修理につながる可能性があります。一つでも当てはまる場合は、すぐに専門家に相談しましょう。
サイン1:エンジンからの異音・白煙・振動
車の心臓部であるエンジンからの異常は、最も注意すべきサインです。
- 異音: アイドリング中に「ガラガラ」「カンカン」といった金属がぶつかるような音がする場合、エンジン内部で深刻なトラブルが起きている可能性があります。特にオイル不足や劣化が原因で発生しやすく、放置するとエンジンが焼き付いて走行不能になる危険性が高いです。
- 白煙: マフラーから白い煙がモクモクと出る場合、エンジンオイルが燃焼室に入り込んで一緒に燃えている「オイル上がり」や「オイル下がり」という状態が考えられます。これもエンジンの寿命が近いサインであり、修理には高額な費用がかかります。
- 振動・加速不良: 信号待ちで車がブルブルと大きく震えたり、坂道でアクセルを踏んでも力なく失速したりする場合、エンジンが正常に燃焼していない可能性があります。燃費の悪化にもつながり、最終的にはエンジンそのものの故障に至るケースも少なくありません。
これらの症状が出た場合、エンジンの載せ替えやオーバーホール(分解修理)が必要になることもあり、その費用は30万円~70万円以上と非常に高額になります。
サイン2:トランスミッションの異常(変速ショック・異音)
エンジンが生み出した力をタイヤに伝える重要な役割を担うのがトランスミッション(CVTなど)です。
- 変速ショック: アクセルを踏んで加速する際に「ガクン」と大きな衝撃が来る場合、トランスミッション内部に問題が発生している可能性があります。
- 異音・滑り: 走行中に「ウィーン」という唸るような音が続いたり、アクセルを踏んでエンジンの回転数だけが上がり、スピードがついてこない「滑り」の症状が出たりするのも危険なサインです。
トランスミッションの故障も走行不能に直結します。修理は載せ替えが基本となり、費用相場は25万円~60万円程度と、こちらも大きな出費を覚悟しなければなりません。
サイン3:足回りからの異音・走行中の不安定感
安全な走行を支える足回りからの異常も見逃せません。
- 異音: 段差を乗り越える際に「ゴトゴト」「コトコト」といった音がする場合、サスペンションやそれを支えるゴム部品(ブッシュ)が劣化しているサインです。また、走行中に速度を上げると「ゴー」という音が大きくなる場合は、タイヤの回転を支えるハブベアリングの摩耗が考えられます。
- 走行中の不安定感: ハンドルが左右に取られたり、車体がフワフワと揺れるように感じたりする場合、ショックアブソーバーという衝撃を吸収する部品が寿命を迎えている可能性があります。
足回りの異常は、乗り心地の悪化だけでなく、最悪の場合、走行中にタイヤが外れるなどの重大な事故につながる危険性もあります。ショックアブソーバー4本の交換で5万円~15万円、ハブベアリングの交換は1箇所あたり3万円~7万円が費用の目安です。
サイン4:ブレーキの効きの悪化や異音
ブレーキは命を守る最重要部品です。少しでも異常を感じたら、ただちに点検が必要です。
- 異音: ブレーキを踏んだ時に「キーキー」という高い音がする場合、ブレーキパッドの残量が少なくなっていることを知らせるサインです。これを放置し、「ゴーッ」という金属が擦れるような音に変わったら末期症状。ブレーキローターも損傷し、修理費用が高額になります。
- 効きの悪化: ブレーキペダルを踏んだ時に、以前より深く踏み込まないと効かない、またはスポンジを踏むようなフカフカした感触がある場合、ブレーキフルードの漏れや劣化が考えられ、非常に危険な状態です。
ブレーキパッドの交換は1万円~3万円程度で済みますが、ローターまで交換となると費用はさらに数万円上乗せされます。
サイン5:エアコンの不調や電装系のトラブル
直接走行に関わらないからと油断しがちなのが電装系のトラブルです。
- エアコンの不調: 「エアコンの風は出るけど全く冷えない」という場合、コンプレッサーの故障が考えられます。特に夏場の故障は快適性を著しく損ないます。修理費用は8万円~15万円と高額になりがちです。
- パワーウィンドウの故障: 窓の開閉ができなくなると、料金所の支払いや換気の際に非常に不便です。モーターの故障が原因であることが多く、修理には数万円かかります。
これらの電装系のトラブルは、車の基幹システムに影響を与えるバッテリーやオルタネーター(発電機)の劣化が原因で発生することもあります。一つの不調が、より大きな故障の前兆である可能性も考慮しましょう。
【コラム】人気車種別!注意したい故障事例
車種によって、壊れやすい箇所に特徴がある場合があります。ここでは人気の3車種で報告が多い故障事例をご紹介します。
| 車種 | よく報告される故障箇所 | 修理費用の相場 | 対策・注意点 |
|---|---|---|---|
| ダイハツ・タント | CVT、電動スライドドア、エアコンコンプレッサー | CVT:20~40万円 スライドドア:3~5万円 | CVTフルードの定期的な交換が重要。スライドドアのレールは清潔に保つ。 |
| ホンダ・N-BOX | 燃料ポンプ、CVT、エアコンコンプレッサー | 燃料ポンプ:3~5万円 CVT:30~50万円 | リコール情報が出ていないか定期的に確認する。CVTの異常を感じたら早めに点検を。 |
| スズキ・スペーシア | CVT、エアコンコンプレッサー、バックカメラ | CVT:20~40万円 バックカメラ:2~4万円 | N-BOX同様、CVTのメンテナンスが鍵。電装系の不具合は早めに相談する。 |
ご自身の愛車に特有の弱点を知っておくことも、寿命を管理する上で非常に役立ちます。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺いつもと違う音や動きを感じたら「気のせい」で済ませず、すぐに点検へ。
- エンジンやブレーキの異音・白煙・振動は危険サイン。
- トランスミッションや足回りの不具合は修理費が高額になる傾向。
- 不調の放置は事故やさらなる高額修理を招くリスクがある。
【家計を守る】損しない軽自動車の買い替えタイミングは?
![損しない軽自動車の買い替えタイミングは経済性で決まる - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/損しない軽自動車の買い替えタイミングは経済性で決まる-1024x683.jpg)
愛着のある車に長く乗りたい気持ちは大切ですが、家計を守るためには経済的な視点も欠かせません。「まだ乗れる」が「乗り続けると損」に変わるタイミングは、主に「税金」「維持費」「車の価値」の3つの要素によって決まります。このタイミングを見極めることが、賢いカーライフ計画の鍵となります。
タイミング1:【増税】13年目の軽自動車税・重量税アップ
車は環境への負荷を考慮し、新車登録から一定の年数が経過すると税金が高くなる仕組みになっています。軽自動車の場合、その節目となるのが「13年」です。
| 税金の種類 | 13年未満 | 13年経過後 | 18年経過後 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車税(年額) | 10,800円 | 12,900円 (約20%UP) | 12,900円 |
| 自動車重量税(2年車検時) | 6,600円 | 8,200円 (約24%UP) | 8,800円 (約33%UP) |
このように、13年を超えると毎年支払う軽自動車税と、車検ごとに支払う自動車重量税の両方が重課されます。特に自動車重量税は18年を超えるとさらに高くなります。この増税は、車を所有している限りずっと続く負担です。12回目の車検(11年目)や13年目を迎える前は、買い替えを検討する大きなきっかけの一つと言えるでしょう。
タイミング2:【高額修理】車検費用が高くなる前
車検は2年ごとに必ずやってきますが、年数が経つにつれてその内容は大きく変わってきます。新車から3回目(7年目)や4回目(9年目)の車検あたりから、これまで交換してこなかった部品の寿命が次々とやってきます。
例えば、バッテリーやタイヤといった消耗品に加え、先述したサスペンションやブレーキ関連、ウォーターポンプなど、交換費用が5万円~10万円以上かかる高額な部品の交換時期が重なることがあります。その結果、基本的な車検費用に加えて10万円、20万円といった追加費用が発生し、車検代が予想以上に膨らんでしまうケースは少なくありません。車検の見積もりを取った際に、修理費が高額になった時も買い替えの好機です。
タイミング3:【価値の崖】リセールバリューが大きく下がる前
愛車の価値、つまりリセールバリュー(再販価値)は、買い替え時の大切な資金源になります。この価値は年々下がっていきますが、特に大きく価値が下がる「崖」のようなタイミングが存在します。
- 3年落ち: 初回の車検を迎えるタイミング。多くの車が中古車市場に出回り始めます。
- 5年落ち: 2回目の車検。走行距離が5万kmを超え、メーカーの特別保証が切れる時期でもあり、価値が大きく下がります。
- 7年落ち以降: 7年、9年と年式が古くなるにつれて価値の下落は緩やかになりますが、10年を超えると多くの車種で査定額がほとんどつかなくなる傾向があります。
人気車種は古くても価値が残りやすいですが、それでも年数には勝てません。少しでも高く売れるうちに売却し、次の車の購入資金に充てるのは非常に賢い選択です。
【シミュレーション】9年落ちタント「乗り続けコスト」vs「買い替えコスト」
ここで、ペルソナである佐藤さんのケース(9年落ち、9.5万kmのタント)を例に、今後4年間(車検2回分)のコストを比較してみましょう。
【A】今のタントにあと4年乗り続ける場合
- 自動車税:10,800円×2年 + 12,900円×2年 = 47,400円
- 重量税:6,600円(11年目車検) + 8,200円(13年目車検) = 14,800円
- 車検基本料+整備費:約150,000円×2回 = 300,000円
- 想定される高額修理(オルタネーター等):約80,000円
- 4年間の合計コスト:約442,200円
【B】今すぐ同程度の中古車(7年落ちタント)に買い替える場合
- 車両購入費用(現在のタント下取り価格を充当):約600,000円
- 自動車税:10,800円×4年 = 43,200円
- 重量税:6,600円×2回 = 13,200円
- 車検基本料+整備費:約100,000円×2回 = 200,000円
- 4年間の合計コスト:約856,400円
一見すると乗り続ける方が安く見えますが、4年後にはAのタントは13年落ちとなり価値がほとんどゼロになる一方、Bのタントは11年落ちでまだ価値が残っています。また、Aは突然のさらなる高額修理のリスクを常に抱えています。安全性や快適性の向上も考慮すると、買い替えが有力な選択肢になることがわかります。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺次の車検前に修理内容と税金負担をシミュレーションして、買い替えと比較を。
- 13年を超えると税金が一気に増え、コストがかさむ。
- 車検費用が10万円以上跳ね上がる年も買い替えの目安。
- リセールバリュー(下取り額)は5年・7年・10年で大きく変化する。
【まだ乗りたい人へ】愛車の寿命を5年延ばすメンテナンス術
![愛車の寿命を5年延ばすメンテナンス術 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/愛車の寿命を5年延ばすメンテナンス術-1024x683.jpg)
「経済的なタイミングもわかるけど、やっぱり今の車に愛着があるから、できるだけ長く乗りたい」。そう思う方も多いでしょう。ご安心ください。日頃のちょっとした心がけと適切なメンテナンスで、軽自動車の寿命は確実に延ばせます。ここでは、誰でも実践できるメンテナンス術をご紹介します。
基本のキ:エンジンオイルの定期交換
人間で言えば血液にあたるエンジンオイル。その役割は、潤滑、冷却、洗浄など多岐にわたります。このオイルの管理こそが、エンジンを長持ちさせる最も重要なポイントです。オイルは走行するうちに汚れたり、劣化したりして性能が落ちてしまいます。
交換の目安は、走行距離5,000km毎、または6ヶ月毎のどちらか早い方です。あまり車に乗らない方でもオイルは自然に酸化するため、期間での交換を忘れないようにしましょう。また、オイル交換2回に1回は、汚れをろ過する「オイルフィルター(エレメント)」も一緒に交換するのがおすすめです。
消耗品の適切な交換サイクル一覧
車は多くの消耗部品で成り立っています。これらの部品を適切なタイミングで交換していくことが、大きな故障を未然に防ぎ、結果的に車の寿命を延ばすことにつながります。
| 消耗品 | 交換時期の目安 | 交換を怠るとどうなる? |
|---|---|---|
| タイヤ | 4~5年 or 残り溝1.6mm | スリップ事故の危険性、燃費悪化 |
| バッテリー | 2~3年 | 突然のエンジン始動不能 |
| ブレーキパッド | 走行距離3~5万km | ブレーキが効かなくなり重大事故に |
| CVTフルード | 走行距離2~4万km | 変速ショック、燃費悪化、CVT本体の故障 |
| スパークプラグ | 走行距離2万km(ノーマル) 10万km(長寿命タイプ) | エンジン不調、加速不良、燃費悪化 |
| エアフィルター | 走行距離2~3万km | エンジンのパワーダウン、燃費悪化 |
これらの部品は車検時に点検されることが多いですが、日頃から気にかけておくことが大切です。特にCVTフルードは「無交換で良い」と言われることもありますが、長く乗りたいのであれば定期的な交換を強く推奨します。
寿命を縮めるNGな運転・長持ちさせる運転のコツ
日々の運転の仕方一つで、車にかかる負担は大きく変わります。
【寿命を縮めるNGな運転】
- 急発進・急ブレーキ・急ハンドル: エンジンやブレーキ、タイヤに過度な負担をかけ、部品の摩耗を早めます。
- 短距離走行の繰り返し: エンジンが十分に温まる前に停止する「チョイ乗り」は、エンジン内部に水分や汚れが溜まりやすく、オイルの劣化を早める原因になります。
- エンジンをかけてすぐの発進: 特に冬場は、エンジンをかけてから30秒~1分ほど暖機運転をすることで、エンジンへの負担を軽減できます。
これらの運転を避け、常に「丁寧でスムーズな運転」を心がけることが、愛車を長持ちさせる一番の秘訣です。月に一度でも良いので、少し長めの距離を走らせてあげると、エンジン内部のコンディションを良好に保つ助けになります。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺「月1メンテナンス日」を作って、オイル・タイヤ・ブレーキをチェックする習慣を。
- エンジンオイルは血液と同じ。劣化すると全体にダメージが広がる。
- 消耗品の交換時期を守ることがトラブル防止の第一歩。
- 運転のクセ(急発進や短距離走行)は寿命を縮める原因になる。
寿命を迎えた軽自動車の3つの賢い手放し方
![寿命を迎えた軽自動車の3つの賢い手放し方 - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/寿命を迎えた軽自動車の3つの賢い手放し方-1024x683.jpg)
様々な検討を重ね、愛車を手放す決断をした場合、その手放し方にも賢い選択肢があります。「もう古いから価値がない」と諦めてしまうのは早いかもしれません。ここでは、車の状態に応じた3つの選択肢をご紹介します。
選択肢1:まだ価値があるなら「買取査定」
「10年落ち、10万km超えだから値段なんてつかないだろう」と思っていませんか?実は、車種や車の状態によっては、古くても十分に値段がつくケースがあります。特に、N-BOXやジムニーのような人気車種、あるいは整備記録がしっかり残っている車は、中古車市場で需要があります。
ディーラーでの下取りは手続きが楽ですが、査定額は低めになる傾向があります。少しでも高く売りたいなら、複数の買取業者に査定を依頼できる「一括査定サービス」の利用がおすすめです。業者間で競争が生まれるため、思わぬ高値がつく可能性があります。
選択肢2:動かない・価値がないなら「廃車買取」
故障して動かなくなってしまった車や、買取査定で値段がつかなかった車でも、諦める必要はありません。そんな時は「廃車買取業者」に相談しましょう。
車は鉄資源の塊であり、また、使える部品(リサイクルパーツ)も残っています。そのため、廃車買取業者は「車そのもの」ではなく「資源」として買い取ってくれます。面倒な廃車手続きを代行してくれ、レッカー代も無料になることがほとんどです。自分で廃車手続きをするよりも、手間なく、かつ数万円のプラスになる可能性が高い方法です。
選択肢3:修理して乗り続ける
限界サインが出ていても、その修理箇所や費用によっては、修理して乗り続けるという選択肢ももちろんあります。特に、エンジンやトランスミッションといった基幹部分ではなく、比較的安価な部品交換で済む場合です。
この判断で重要なのは、信頼できる整備工場に相談することです。修理にかかる費用と、その修理によってあと何年安心して乗れるのかをプロの視点からアドバイスしてもらいましょう。その上で、今後発生しうる他の修理リスクや、乗り続けることでかかる維持費(税金など)を天秤にかけ、総合的に判断することが大切です。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺一括査定サービスなどを使い、手放す際は複数の選択肢を比較しましょう。
- 古くても需要のある車種は意外と高値で売れる可能性がある。
- 動かない車でも、鉄資源や部品として価値がある。
- 修理して乗る選択肢も、信頼できる整備士の判断がカギになる。
まとめ:あなたの愛車は「まだ乗る?」「買い替える?」
![あなたの愛車はまだ乗る買い替える - HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/あなたの愛車はまだ乗る買い替える-1024x683.jpg)
今回は、軽自動車の寿命について、年数や走行距離といった基本的な目安から、プロが見る危険な限界サイン、そして家計に優しい買い替えタイミングまでを詳しく解説しました。
軽自動車の寿命は、技術の進歩により平均16年以上と非常に長くなっています。しかし、本当の寿命は数字だけで決まるものではありません。最も大切なのは、愛車の状態を正しく把握し、安全面と経済性の両方から最適なタイミングを判断することです。
この記事を読んで、ご自身の愛車が「まだ乗る」段階なのか、それとも「買い替える」べき時期に来ているのか、判断のヒントが見つかったのではないでしょうか。どちらの結論に至ったとしても、次の行動は明確です。
- 「まだ乗る」と決めた方: まずは信頼できる整備工場で愛車をしっかり点検してもらい、必要なメンテナンスの計画を立てましょう。
- 「買い替える」と決めた方: まずは愛車が今いくらで売れるのか、一度オンラインの一括査定などで価値を調べてみることから始めてみましょう。
あなたのカーライフがより安全で、経済的で、豊かなものになることを心から願っています。
![HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/cc3d9ca1-c88b-463e-af8f-67dd29cc5449.png)