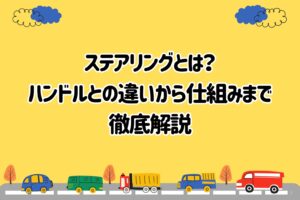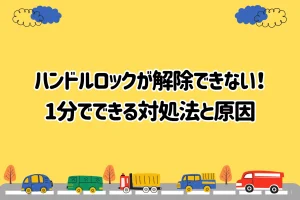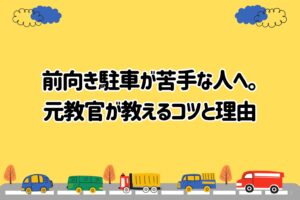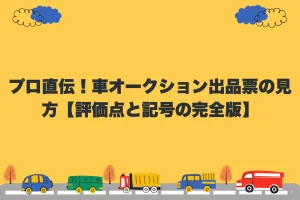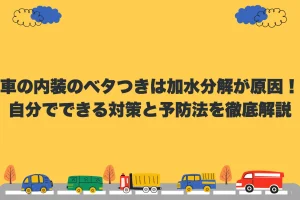いよいよ教習所の集大成、卒業検定(卒検)ですね。「もし落ちたらどうしよう…」「縦列駐車が苦手だな…」など、緊張や不安でいっぱいになっているかもしれません。周りの友達が先に合格していくと、余計に焦ってしまいますよね。
ご安心ください。この記事では、元教習所検定員が、あなたのそんな不安を解消するために卒検一発合格のための全てを徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、卒検の全体像から具体的な攻略法までが明確になり、「これなら自分でも合格できる!」という自信が湧いてきているはずです。卒検は完璧な運転を試す場ではありません。ポイントを押さえた「安全な運転」ができれば、誰でも一発で合格できるのです。一緒に合格への道を切り拓きましょう!

- 減点方式:70点以上で合格、小さなミスは気にしすぎない。
- 安全確認が最重要:検定員に伝わるように大げさに確認。
- 減点されやすい項目TOP5:安全確認・進路変更時の寄せ・停止線・速度維持・乗降時の確認。
- 一発アウト項目:信号無視・一時不停止・歩行者妨害・逆走など。
- メンタルコントロール:ミスを引きずらず、冷静さを保つ。
卒業検定(卒検)は教習所の集大成ですが、完璧な運転は求められていません。採点は100点からの減点方式で70点以上残れば合格。小さなミスは許容範囲で、最重要は「安全確認」。よくある減点項目は確認不足・合図忘れ・停止線オーバーなど。一発アウトとなる信号無視や歩行者妨害を避ければ合格率は非常に高く(97%以上)。当日はリラックスし、焦らず安全運転をアピールすることが大切です。
まずは落ち着いて!卒業検定(卒検)の基本を知ろう
の基本を知ろう-1024x683.jpg)
不安の多くは「何が起こるか分からない」ことから生まれます。まずは卒検がどのようなものか、基本をしっかり理解して、心の準備を整えましょう。
卒検当日の流れをシミュレーション
卒検当日は、朝から慌てないように全体の流れを頭に入れておきましょう。教習所によって多少の違いはありますが、一般的には以下のような流れで進みます。
- 集合・受付: 指定された時間に集合し、受付を済ませます。免許証を持っている場合は忘れずに持参しましょう。
- 検定の説明: 検定員から試験コース、注意事項、採点基準などの説明を受けます。ここで分からないことがあれば、遠慮なく質問してください。
- 検定開始: 自分の順番が来たら、検定員と同乗者を乗せて運転を開始します。通常、他の受験者も後部座席に同乗します。
- 路上検定〜場内検定: まずは路上コースを走行し、教習所に戻ってから縦列駐車や方向転換などの場内課題を行います。
- 合格発表: 全員の検定が終了した後、合格者が発表されます。
- 卒業式・書類交付: 合格者は、卒業証明書などの書類を受け取り、今後の手続きについての説明を受けます。
この流れを知っておくだけでも、当日の心の余裕が大きく変わりますよ。
卒検の採点方法は「減点方式」
卒検の採点は100点満点からの減点方式で行われ、最終的に70点以上残っていれば合格となります。つまり、30点分はミスが許されるということです。小さなミスを一つ二つしたからといって、すぐに不合格になるわけではありません。
この「減点方式」を理解しておくことは、精神的に非常に重要です。「完璧に運転しなきゃ」と気負いすぎると、かえって緊張で体が硬くなり、普段通りの運転ができなくなってしまいます。「多少のミスは大丈夫」と心に余裕を持つことが、合格への第一歩です。
卒検の合格率はどれくらい?
「卒検は難しい試験なのでは?」と心配になるかもしれませんが、実は合格率は非常に高いです。警察庁の運転免許統計(令和5年版)によると、指定自動車教習所卒業者の合格率は、普通免許(AT限定)で97.5%にも上ります。
これは、教習所でしっかり技術を学び、検定に臨めるレベルだと判断された人(みきわめ合格者)が受ける試験だからです。あなたも、指導員から「合格できるレベル」と認められているからこそ、卒検を受けられるのです。自信を持って、教習で学んだことを発揮しましょう。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺「「満点狙い」ではなく「安全第一」で臨みましょう。
- 採点は「減点方式」で合格ラインは70点。
- 路上走行と場内課題(縦列駐車など)がセット。
- 合格率は97%以上と非常に高い。
これだけは避けたい!卒検の減点項目と一発アウト(中止項目)
-1024x683.jpg)
卒検に合格するためには、「何をすれば加点されるか」ではなく、「何をすると減点されるか」を知ることが最も重要です。ここでは、特に注意すべき減点項目と、一発で不合格となる「中止項目」を解説します。
【一覧表】主な減点項目と点数
卒検でよくある減点項目を一覧表にまとめました。自分の運転を振り返りながら、どの項目でミスをしやすいか確認しておきましょう。
| 減点項目 | 点数 | 具体的な状況例 |
|---|---|---|
| 安全確認不履行 | -10点 | 発進時、右左折時、進路変更時に目視確認を怠る |
| 合図不履行 | -5点 | 進路変更や右左折の30m(3秒)手前でウインカーを出さない |
| 巻き込み防止措置不履行 | -10点 | 左折時に左後方の安全確認をせず、バイクなどを巻き込む危険がある |
| 速度超過 | -10点 | 制限速度を大幅に超えて走行する |
| 速度維持違反 | -5点 | 理由なくノロノロ運転を続け、円滑な交通を妨げる |
| 停止線不停止 | -10点 | 停止線を大幅に超えて停止する |
| 進路変更禁止違反 | -10点 | オレンジ色の車線を越えて進路変更する |
| 脱輪(小) | -5点 | 縁石に軽く乗り上げる、または接触する |
小さなミスが命取りに?減点されやすいポイント TOP5
上記の項目の中でも、特に多くの受験者が減点されてしまうポイントがあります。以下の5つは重点的に意識して運転しましょう。
- 安全確認: 最も減点されやすい項目です。検定員に「見ていますよ」とアピールするため、首をしっかり動かして大げさなくらいに確認しましょう。
- 進路変更・右左折時の寄せ: 進路変更や右左折の際は、早めにウインカーを出し、スムーズに車線の中央や適切な位置に車両を寄せることが大切です。
- 停止線の遵守: 停止線の直前でしっかり停止しましょう。停止線を行き過ぎるのはもちろん、手前すぎても減点対象になることがあります。
- 適切な速度維持: 周囲の流れに乗り、指定速度内でメリハリのある運転を心がけましょう。遅すぎると「円滑な交通の妨げ」と判断される場合があります。
- 乗降時の確認: 運転席に乗り込む前と降りた後も採点対象です。車の前後を確認してから乗り込み、後方の安全を確認してからドアを開けるまで、最後まで気を抜かないようにしましょう。
一発アウト!危険行為とみなされる「中止項目」
減点とは別に、たった一度でも行うと即座に検定が中止(不合格)となる項目があります。これらは重大な事故に直結する危険行為です。
- 信号無視
- 一時不停止(指定場所で完全に停止しない)
- 逆走
- 歩行者等保護違反(横断歩道で歩行者を妨害する)
- 踏切不停止等
- 縁石への乗り上げや接触(大)
- ポールなどへの接触
- 検定員の補助ブレーキ・ハンドル操作
これらの項目は、普段の教習で「絶対にやってはいけない」と教わってきた基本的なことばかりです。落ち着いて運転すれば、まず起こすことはありません。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺教習で習った「絶対NG行為」を忘れなければ合格に近づきます。
- 減点は確認不足や合図忘れなど日常的なミスが中心。
- 中止項目は重大事故につながる行為(信号無視、歩行者妨害など)。
- 減点より「一発アウト」を避けることが最優先。
元教官が伝授!卒検一発合格のための10のコツ【運転技術編】

ここからは、元検定員の視点から、一発合格をグッと引き寄せるための具体的な運転技術のコツをお伝えします。
【最重要】安全確認は「やりすぎ」なくらい徹底する
検定員が最も重視しているのは「安全確認」です。あなたが周囲の状況をしっかり認識し、危険を予測して運転しているかを見ています。ルームミラー、サイドミラー、そして直接の目視。これを一連の流れとして、特に以下の場面では徹底しましょう。
- 発進前
- 進路変更時
- 右左折時
- 交差点通過時
「自分は見ているつもり」でも、検定員に伝わらなければ意味がありません。顎を引いて首をしっかり左右に振るなど、少し大げさなくらいのアクションを心がけることが、確実なアピールに繋がります。
メリハリのある加減速を意識する
安全な範囲で、アクセルを踏むべきところはしっかり踏み、速度を出すことが大切です。直線道路などで周囲の交通を妨げるほどノロノロ運転していると、「判断力が低い」「交通状況を理解していない」と見なされ、減点対象になる可能性があります。
もちろん、交差点の手前やカーブ、障害物がある場所では、事前にしっかり減速する必要があります。この「走る・止まる」のメリハリが、スムーズで安定した運転と評価されます。
正しい運転姿勢をキープする
緊張すると、無意識にハンドルにしがみついたり、前屈みになったりしがちです。しかし、これは視野を狭め、正確なハンドル操作を妨げる原因になります。
検定開始前に、シートポジション、ミラーの角度、ヘッドレストの高さをしっかり自分に合わせましょう。背筋を伸ばし、リラックスした状態でハンドルを握ることで、心にも余裕が生まれます。基本中の基本ですが、これが安定した運転の土台となります。
縦列駐車・方向転換の攻略法
多くの人が苦手とする縦列駐車と方向転換。しかし、手順さえ覚えてしまえば怖くありません。ここでは基本的な手順の例を紹介します。(※教習所によって目印の取り方などが異なりますので、必ず教習所で習った方法を優先してください)
【縦列駐車のコツ】
- 駐車スペースの前の車と約1mの間隔をあけて平行に停車し、後端を合わせる。
- ハンドルを左に全て切り、バックする。右のサイドミラーに、後ろの車の全体が映ったら停止。
- ハンドルをまっすぐに戻し、そのままバック。自車の左後方が駐車スペースの角に来たら停止。
- ハンドルを右に全て切り、ゆっくりバック。車体が平行になったら停止し、ハンドルを戻す。
【方向転換(右バック)のコツ】
- 通路の左側にできるだけ寄せ、車体後方がスペースの入り口を少し過ぎたあたりで停止。
- ハンドルを右に全て切り、ゆっくりバック。
- 車体がスペースと平行に近づいたら、ハンドルをまっすぐに戻しながらバック。
- スペース内に収まったら停止。
最も大切なのは焦らないことです。もし「まずい!」と思ったら、一度停止して状況を確認しましょう。切り返しは1回までなら減点されない場合がほとんどです。慌てて接触するより、落ち着いて切り返す方が断然良い選択です。
S字・クランクは「車両感覚」を意識してゆっくり通過
S字やクランクでは、内輪差(後輪が前輪より内側を通ること)を意識することが重要です。特にカーブでは、前輪が通過できても後輪が縁石に接触するケースが多く見られます。
これを防ぐコツは、カーブに入る前にできるだけ外側に寄せること。例えば左カーブなら、進入前に右に寄っておくことで、左後輪が縁石に当たるのを防げます。速度はできるだけ落とし、常に先の縁石を見ながら、車両がどのように動くかをイメージしてハンドルを操作しましょう。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺「落ち着いて切り返す勇気」が失敗を防ぎます。
- 安全確認は首をしっかり動かしてアピール。
- メリハリある加減速でスムーズに。
- 縦列駐車やS字は焦らずゆっくり通過。
緊張は最大の敵!卒検当日のためのメンタルコントロール術

どんなに運転技術があっても、過度な緊張はパフォーマンスを低下させます。ここでは、平常心で卒検に臨むためのメンタル術をご紹介します。
前日はしっかり睡眠をとる
「明日は卒検だ…」と不安で夜更かししてしまうのは逆効果です。睡眠不足は集中力や判断力を著しく低下させ、思わぬミスを引き起こします。前日はコースを軽くイメージトレーニングする程度にとどめ、早めにベッドに入って十分な睡眠を確保しましょう。体調を万全に整えることも、合格のための重要な準備の一つです。
試験官(検定員)は敵じゃない!
助手席に座る検定員を「自分の運転を採点する怖い人」だと考えると、余計に緊張してしまいます。検定員はあなたの運転の粗探しをしているわけではありません。「あなたが安全に運転できるかを確認し、社会に送り出す責任者」であり、ある意味ではあなたの安全を守る味方です。
検定が始まる前には「よろしくお願いします!」とハキハキ挨拶し、指示が聞こえたら「はい」と返事をするだけでも、コミュニケーションが生まれ、場の空気が和らぎます。
ミスをしても引きずらない
卒検中に縁石に少し接触してしまったり、ウインカーを出し忘れたり、小さなミスは誰にでも起こり得ます。ここで最もやってはいけないのが、一つのミスを引きずってパニックになることです。
「あぁ、もうダメだ」と思った瞬間、集中力が切れ、次の操作でさらに大きなミスを犯してしまいます。減点方式なので、小さなミスはまだ挽回可能です。「終わったことは仕方ない、次で取り返そう」と気持ちを切り替えて、目の前の運転に集中しましょう。
分からないことは正直に質問する
検定中にコースが分からなくなってしまうこともあります。そんな時、勝手に判断して進路を変えたり、急停車したりするのは絶対にNGです。
「次のコースが分からなくなりました」と、正直に検定員に尋ねましょう。道を間違えること自体は減点対象ではありません。検定員が正しいコースに誘導してくれますので、落ち着いて指示に従えば大丈夫です。分からないことを素直に聞けるのも、安全運転に必要なスキルの一つです。
 HUBRIDE小野寺
HUBRIDE小野寺「多少のミスは大丈夫」と心で唱えると落ち着けます。
- 緊張は最大の敵、前日は睡眠を優先。
- 検定員は敵ではなく、安全確認のパートナー。
- ミスを引きずらないことが次の成功につながる。
もし卒検に落ちてしまったら?不安を解消【Q&A】

万が一の結果も想定しておくことで、心の負担は軽くなります。もし卒検に落ちてしまった場合の対応について知っておきましょう。
- 再試験までの流れと期間は?
-
卒検に不合格となった場合、すぐに再試験を受けることはできません。法律で、最低1時限の補習教習を受けることが義務付けられています。補習で自分の弱点を克服した後、再度、卒検の予約を取る流れになります。教習所の混雑状況にもよりますが、通常は数日から1週間ほどで再試験を受けられることが多いです。
- 追加料金はいくらかかる?
-
追加でかかる費用は、主に「補習教習料金」と「再検定料金」です。教習所によって金額は異なりますが、一般的には合計で10,000円〜15,000円前後が相場となっています。一発で合格すれば不要になる費用なので、やはり集中して臨みたいところですね。
- 何回まで受験できる?
-
卒検の受験回数に上限はありません。しかし、注意しなければならないのが「教習期限」です。教習を開始してから9ヶ月以内に全ての教習(卒業検定合格まで)を終えなければならず、この期限を過ぎると、それまでの教習が無効になってしまいます。期限が迫っている場合は、特に注意が必要です。
まとめ:卒検は「安全運転」のアピールの場!自信を持って臨もう

最後に、卒検一発合格のための要点をまとめます。
- 卒検は100点満点からの減点方式。70点以上で合格なので完璧を目指す必要はない。
- 最も重要なのは「安全確認」。検定員に伝わるように、少し大げさなくらいアクションする。
- 一発アウトの中止項目(信号無視、一時不停止など)さえしなければ、合格のチャンスは十分にある。
- ミスをしても引きずらない。気持ちを切り替え、次の運転に集中することが大切。
卒検は、あなたの運転技術を試す場であると同時に、「これだけ安全に配慮して運転できますよ」とアピールする場でもあります。これまで教習所で学んできた一つひとつの操作を、焦らず、丁寧に実践すれば、結果は必ずついてきます。
この記事をここまで読んだあなたは、もう合格に必要な知識を十分に持っています。あとは自分を信じて、リラックスして臨むだけです。応援しています!
![HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/cc3d9ca1-c88b-463e-af8f-67dd29cc5449.png)